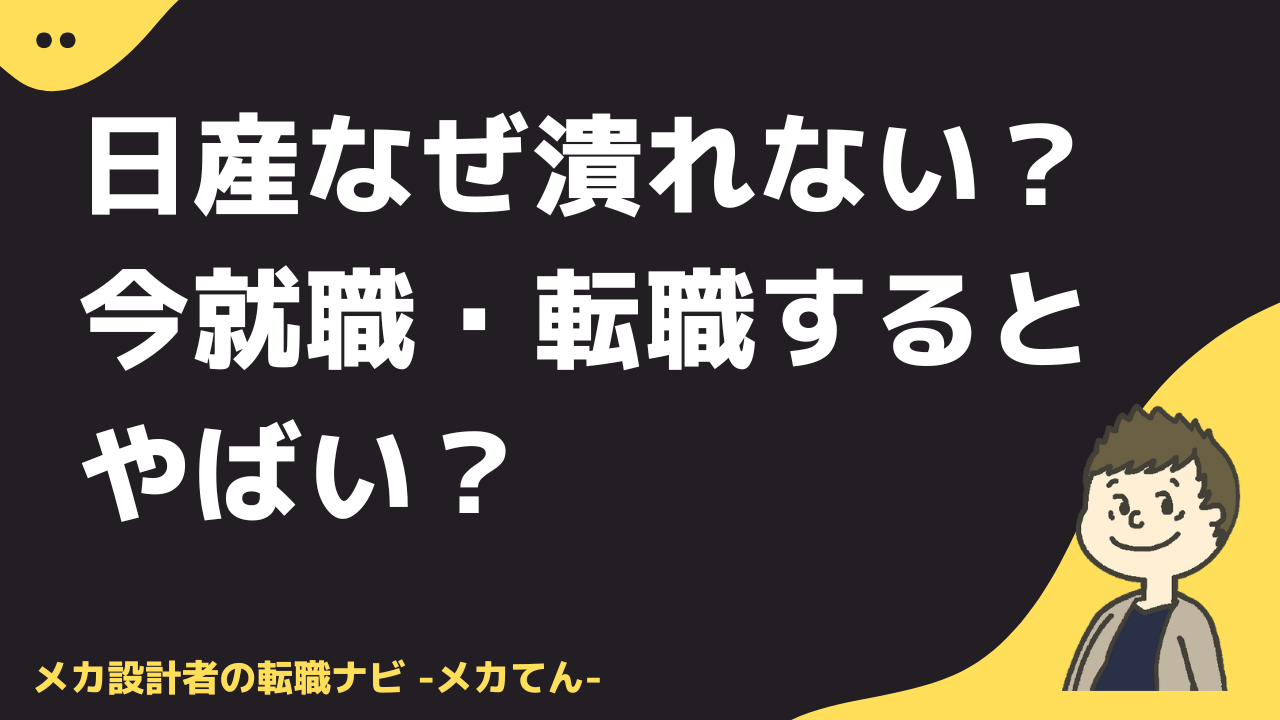結論から言うと、今から日産に転職・就職するのは慎重になるべきです。
一見すると大手メーカーで安定しているように見えますが、内情をよく知ると「本当にここに入って大丈夫?」と不安になるような実態も少なくありません。
この記事では、
- なぜ日産は潰れないのか?
- 今から就職・転職するのは後悔するからやばい?
- 日産に転職して後悔する理由
といったリアルな情報を、詳しく見て行きます。
これから日産をキャリアの選択肢に考えているなら、ぜひ判断材料のひとつにしてみてください。
日産はなぜ潰れない?
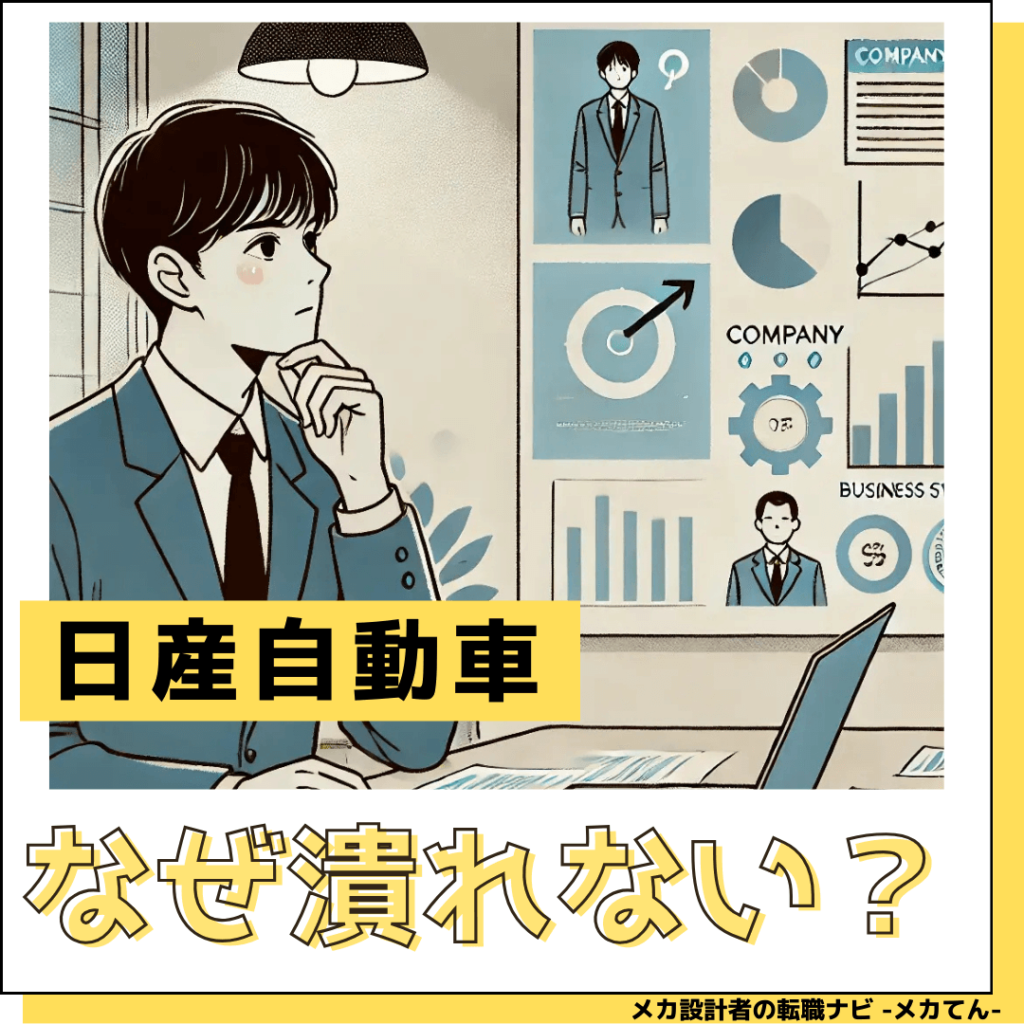
一時は経営危機に瀕した日産ですが、今日に至るまで存続し続けています。
ではなぜ、あれほどゴタゴタの多かった企業が潰れずに残っているのか?
実は、外部から見えにくい“潰れにくい構造”が存在します。
自動車産業の中核を担う「潰せない存在」
日産は、単なる一企業ではなく、日本の基幹産業である自動車業界の一角を担う重要な企業です。
トヨタ、ホンダに続く規模を持ち、サプライヤー(部品メーカー)、販売店、金融、物流など広範囲な産業とつながっています。
日産がもし突然経営破綻すれば、全国の雇用や地域経済に連鎖的な悪影響が及ぶため、国や大手金融機関が黙って見ているわけにはいかないのです。
特に地方の工場が多く、「日産があるから成り立っている町」もあるほど。
これが“潰れそうで潰れない”最大の背景です。
ルノーとの資本提携が「救命装置」に
1999年、経営危機に陥った日産はフランスの自動車大手ルノーから支援を受け、同時にアライアンス(企業連合)を結成しました。
この提携によって、ルノーは日産の株式を保有し、経営にも深く関与。
以降、部品調達や開発費の共有、人員の相互派遣などで両社のコストを削減し、グローバル競争に耐えうる体制を整えました。
現在は三菱も加わり、「日産・ルノー・三菱アライアンス」として世界規模の企業グループとなっています。
この連携が、日産単独ではできない課題への対応力を生み出しているのです。
看板車種とグローバル展開による収益源
国内では「ノート」や「セレナ」「エクストレイル」など、安定した販売実績を持つ車種が存在し、一定の収益基盤を維持しています。
特に「e-POWER」などの電動パワートレイン技術は他社との差別化要素として評価されています。
加えて、北米や中国、東南アジアなど海外市場でも存在感を保っており、世界全体での販売台数が会社の体力を下支えしています。
つまり、国内だけでなくグローバルにリスク分散されているため、特定の地域での業績不振だけでは会社全体が崩れることはない構造になっているのです。
問題を抱えていても「倒産させるリスク」の方が大きい
もちろん、日産には問題が山積しています。
経営の透明性、社内の混乱、ブランドイメージの悪化、人材流出…。
こうした要素だけ見れば「やばい企業」と言われても不思議ではありません。
しかし、だからといって潰してしまえば、国内外に与えるマイナスの方が大きく、関係企業や株主、国にとっても得策とはいえません。
日産は、いわば「表向きは民間企業、中身は半ば“公共インフラ”に近い存在」なのです。
【総括】潰れにくいのは「守られているから」
日産が潰れないのは、業績が常に良いからでも、社内に革新的な力があるからでもありません。
重要なのは、外部とのつながりの中で「潰れてはいけない存在」として守られているからです。
したがって、日産に就職・転職を検討している人は、「潰れない=安泰」という考え方だけでなく、なぜ潰れないのか、その構造を冷静に理解したうえで判断する必要があります。
今から就職しても勝ち組?

結論から言うと、日産への就職が「勝ち組」かどうかは、人によって大きく分かれます。
「安定した大手で働きたい」人には一定のメリットがある一方で、「成長・挑戦・市場価値」を重視する人にとっては、物足りなさやリスクが残る企業でもあります。
大手企業ならではの「待遇・安定感」は確かにある
日産は自動車業界大手ということもあり、給与水準や福利厚生、企業規模は申し分ありません。
たとえば、年収ベースでは平均約700万円〜800万円前後とされており、20〜30代でも同業他社より高水準。
住宅補助や持株会、退職金制度も整っており、働く側としては「生活の安心感」が得られます。
また、知名度のある大企業に入ることで、家族や周囲からの安心感も得やすいです。
これだけを見ると、確かに“勝ち組”と感じる人も多いでしょう。
だが「将来的な不安」や「停滞感」も否めない
一方で、社内の雰囲気やキャリア形成の視点では注意が必要です。
日産は過去のゴーン体制以降、長らく組織が揺れており、現在もその余波を引きずっています。
新規事業や技術革新に向けたスピード感、経営の一貫性にはやや疑問の声があり、
といった声も少なくありません。
また、上層部の入れ替えが続き、現場では意思決定のスピードが遅いという指摘も。
変化を求める人にとっては、やりがいや達成感を得づらい環境とも言えるでしょう。
「勝ち組」の基準はあなたの価値観で変わる
たとえば──
- 堅実に定年まで働きたい → 向いている
- 年功序列でも問題ない → ストレスは少なめ
- 新しいチャレンジや裁量権がほしい → 合わない可能性大
- 外資系のようなスピード感を求める → 期待はずれの可能性あり
日産で「勝ち組」になれるかは、こうした価値観と企業の特徴がどれだけ一致しているかによって決まります。
【総括】勝ち組かどうかは“自分軸”で判断を
日産への就職は、ネームバリューや待遇面では間違いなく「大手の安定」を手にできます。
しかし、個人の価値観やキャリアビジョンによっては、
と感じるリスクもあるため注意が必要です。
もしあなたが「とにかく安定した職場に入りたい」という価値観であれば、日産は十分“勝ち組”になり得る選択肢。
一方で、
といった志向が強いのならば、慎重な判断が求められます。
日産に転職して後悔する理由
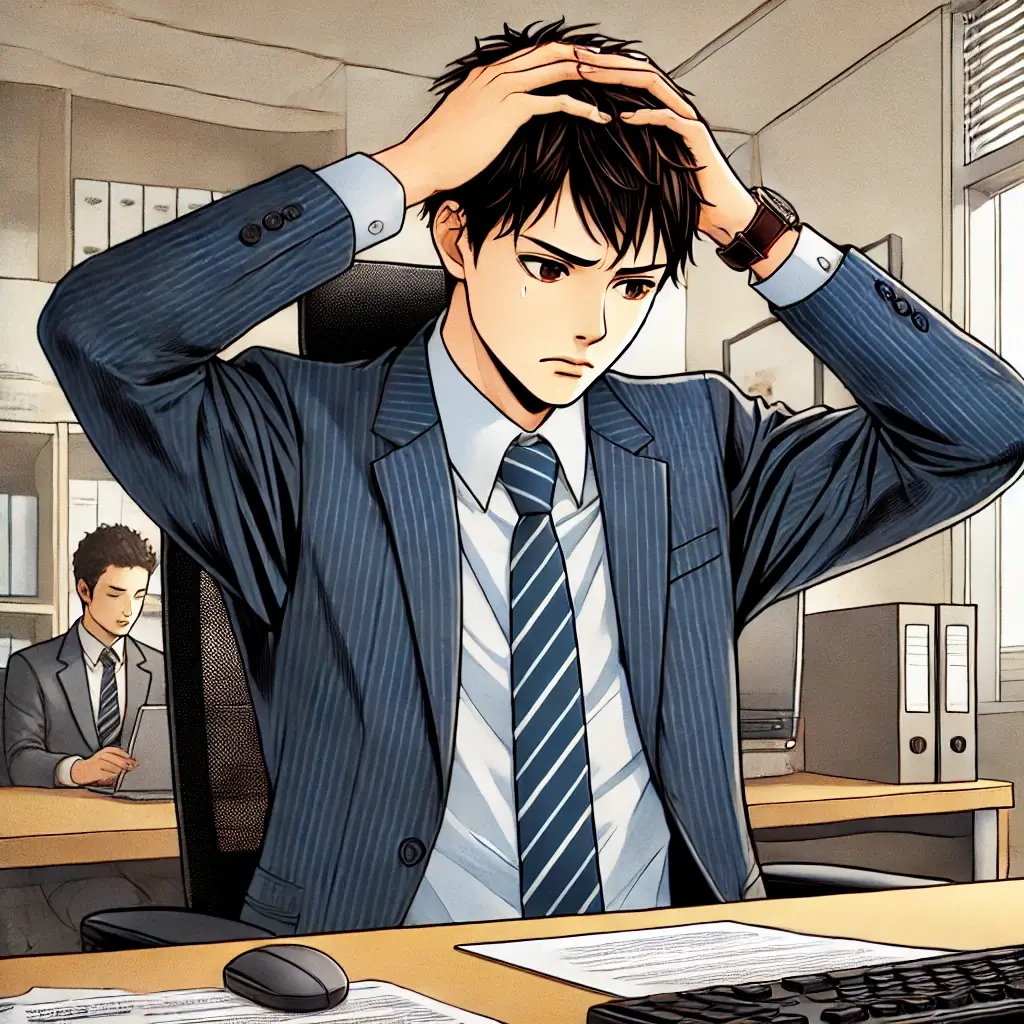
一見すると魅力的な大手企業・日産。
しかし、実際に転職してから「思っていたのと違う…」と後悔する人も少なくありません。
その背景には、職場環境・働き方・組織の特徴に起因する“見えづらい落とし穴”があります。
① 意思決定が遅く、仕事にスピード感がない
日産は長年、海外志向の強い経営方針の中で組織の階層化・官僚化が進んできました。
そのため、現場で良い提案をしても、いくつもの承認プロセスを経ないと動かない…という場面が日常茶飯事。
この「とにかくスピードが遅い文化」にストレスを感じ、転職者が「前職の方がよかった」と感じてしまうことがあります。
② 古い体質・年功序列が根強く残っている
日産は“外資系っぽい”と言われることもありますが、実際の職場環境はかなり日本的です。
特に地方工場や技術部門では、いまだに年功序列や上司の顔色をうかがう風土が色濃く残っており、成果よりも「年次」や「所属部署の派閥」が出世に影響するケースもあります。
中途で入った人にとっては
と感じてしまう場面も。
③ 成長機会やキャリア支援が限定的
意外かもしれませんが、日産では社内のローテーション制度やキャリアアップ支援が必ずしも活発ではありません。
部署異動の自由度は低く、「今の業務を淡々とこなすだけ」という状況になりがち。
という目的を持って入社した人にとっては、物足りなさや焦りを感じる可能性があります。
④ 一部の部門で残業や業務過多が続いている
表向きには「働き方改革」に取り組んでいるものの、実際には部署によって残業が月50時間を超えるような場所もまだ存在します。
特にエンジニアや企画職などでは、慢性的な人員不足とタスクの集中により、業務量が多く「定時帰りなんて無理」という声も。(ただ、実際に毎週定時退社推進日はあります。)
「大手だからワークライフバランスが取れるはず」と期待していた転職者にとって、これも後悔の一因になります。
⑤ “再建中の会社”であることを忘れてはいけない
日産は過去の不正問題やゴーン事件以降、長期的な業績回復を目指している途中の段階です。
確かに業績は改善傾向にありますが、
といった課題も未解決です。
つまり、“会社が安定して見えるのは外から見た一部の印象に過ぎない”こともあるのです。
【総括】転職前に「内部のリアル」を知ることが大事
日産に転職して後悔する人の多くは、「イメージと実態のギャップ」に苦しみます。
たしかに知名度があり待遇も悪くはない企業ですが、その内側には“古さ”や“非効率”という課題も根深く残っています。
転職を検討しているなら、表面的な条件だけで判断せず、OB・OG訪問や口コミ調査などを通じて「リアルな職場の空気感」に触れておくことが、後悔しないためのカギです。
日産の評判が悪い理由

一流メーカーであるはずの日産ですが、ネット上や転職口コミサイトでは
など、ネガティブな声が目立ちます。
その原因は単なる“悪口”ではなく、実際の組織課題や働き方に根拠があるものです。
① ガバナンス不信がいまだに尾を引いている
2018年に発覚したゴーン元会長の不正事件は、日産の信頼性を大きく揺るがしました。
その後も
といったガバナンス面の混乱が続き、企業としての“健全性”に疑問を持たれることに。
こうした状況は社員の士気にも影響し、口コミでは「現場の混乱が続いている」といった声が上がっています。
② 海外依存体質と国内軽視の印象
日産はグローバル戦略を重視するあまり、国内の販売体制やディーラー支援を後回しにしてきた側面があります。
など、ディーラー現場からは不満の声が噴出。
これが結果として「国内ユーザー離れ」や「不人気車種の増加」につながり、一般ユーザーからのブランド評価にも影響を与えています。
③ 組織の硬直化・変化に対する鈍さ
日産はかつて“技術の日産”と呼ばれ、革新性の高いメーカーとして知られていました。
しかし現在は、新しい取り組みに対して保守的な空気が強く、
「改善提案が通らない」
「上層部の意見がすべて」
という組織風土に変化。
これにより、社内外から
といった批判が上がりやすくなっています。
④ 評価制度やキャリアの不透明さ
社員の評価制度に関しても、
「実力より年功」
「上司との関係性がものをいう」
といった声が少なくありません。
特に中途社員や若手社員からは、
「何を基準に評価されているのかが分からない」
「キャリアの道筋が見えない」
といった不満が多く寄せられています。
こうした“先が読めない働き方”は、モチベーション低下や離職意向の増加にもつながっています。
⑤ SNSや口コミでの悪評が拡散しやすい
現代では、実際に働いた人の声がリアルタイムでSNSや口コミサイトに拡散されます。
日産の場合、知名度が高いがゆえに少しの不満が大きく目立ち、
といった強めの表現で伝えられることも。
その結果、「なんとなく評判が悪い会社」という印象が固定化され、新たな応募者にも影響を及ぼしています。
【総括】評判には“実態に基づいた理由”がある
日産の評判が悪いのは、単なる誤解や偏見ではなく、実際に働いた人たちが感じた課題が背景にあります。
ガバナンスの不安、古い体質、評価の不透明さなどが重なり、「働きづらい」という印象が根付いてしまっているのが実情です。
もし就職や転職を検討しているなら、こうした“見えづらい実態”も踏まえた上で、自分に合うかどうかを慎重に判断することが重要です。
日産の現状|退職者が続出しているのか?
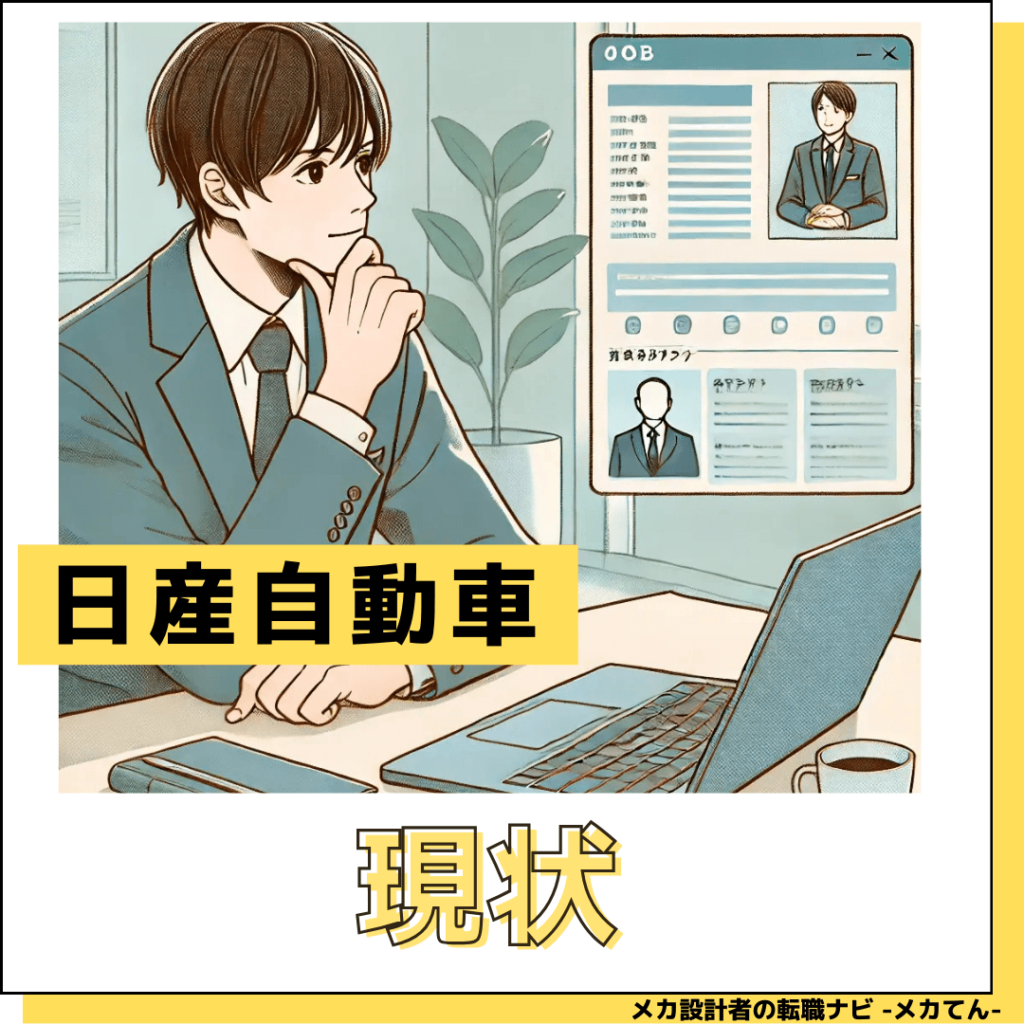
一部の報道や口コミで
「日産は人がどんどん辞めている」
「将来性に不安」
といった声が目立っていますが、実際のところはどうなのでしょうか?
離職傾向が高まっているのは事実であり、その背景には組織の構造的な課題と社員の将来不安が関係しています。
キャリアの展望が描きにくい
日産では、年功序列が色濃く残っている部署と成果主義が導入されている部署が混在しており、キャリアの見通しが立てづらいのが現状です。
「上に行くには年数が必要」
「転職組には出世のチャンスが少ない」
と感じる社員も多く、キャリアアップを望む優秀な人材ほど、より成長機会の多い他社へ流出している傾向があります。
中途採用者が定着しにくい
口コミや体験談によると、中途入社した人の中には
と感じるケースが多く、1〜3年以内で離職する人も少なくありません。
特に外資系企業やベンチャーから転職してきた人ほど、日産の“年功・承認文化”にギャップを感じ、見切りをつけるスピードが早い傾向にあります。
業績回復のプレッシャーが現場を圧迫
業績回復に向けたコストカットや構造改革が続く中で、現場社員の負担は年々増加しています。
人員削減による業務のひっ迫、残業時間の増加、目標数字へのプレッシャーなどが重なり、精神的・肉体的な負担が大きくなっているという声も多数。
このような環境に耐えきれず、体調を崩したり、退職を選ぶ社員も増えつつあります。
若手社員のモチベーション低下
日産では、かつてのような
といった雰囲気が薄れつつあります。
そのため、
と感じる若手社員が増加。
モチベーションの維持が難しくなっており、転職を選ぶケースも見られます。
実際に退職者は増えているのか?
厚生労働省のデータや転職市場の傾向を見ると、日産に限らず自動車業界全体で離職率はやや上昇傾向にあります。
「9000人のリストラ」というニュースも記憶に新しいところです。
特に30代〜40代前半の技術者層が、より安定的かつ柔軟な働き方を求めて、IT業界やEVスタートアップ企業へ流れているのが目立ちます。
日産においても、社内では
といった声がちらほら聞こえるのが現実です。
【総括】日産からの離職は“静かに増えている”
退職者が一斉に辞めるような“パニック”は起きていませんが、水面下で静かに人材が流出しているのが現在の日産の実態です。
特に中途入社者や若手・中堅層の“将来への不安”が離職の主な引き金となっており、企業としての根本的な改革が求められているタイミングにあると言えるでしょう。
就職・転職を考えている方は、「大手だから安心」という先入観にとらわれず、現場のリアルな声や文化的な相性も含めて慎重に判断することが大切です。