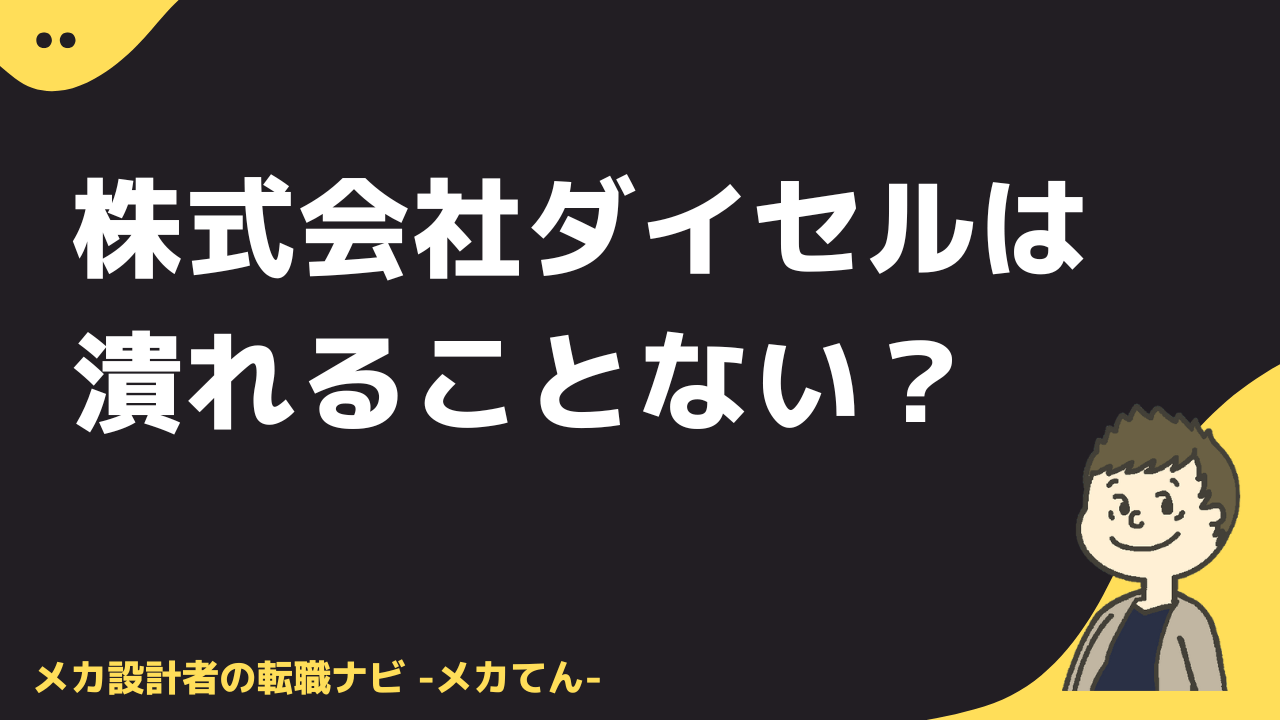結論から言うと、株式会社ダイセルがすぐに潰れる心配はありません。
堅実な業績と革新的な技術開発を背景に、将来性のある優良企業として高い評価を得ています。
とはいえ、「やばい」「しんどい」などの気になる評判があるのも事実。
この記事では、ダイセルの強みや安定性に加え、働き方や年収、採用大学など、転職先として気になる情報を詳しく見て行きます。
株式会社ダイセルは潰れることない?
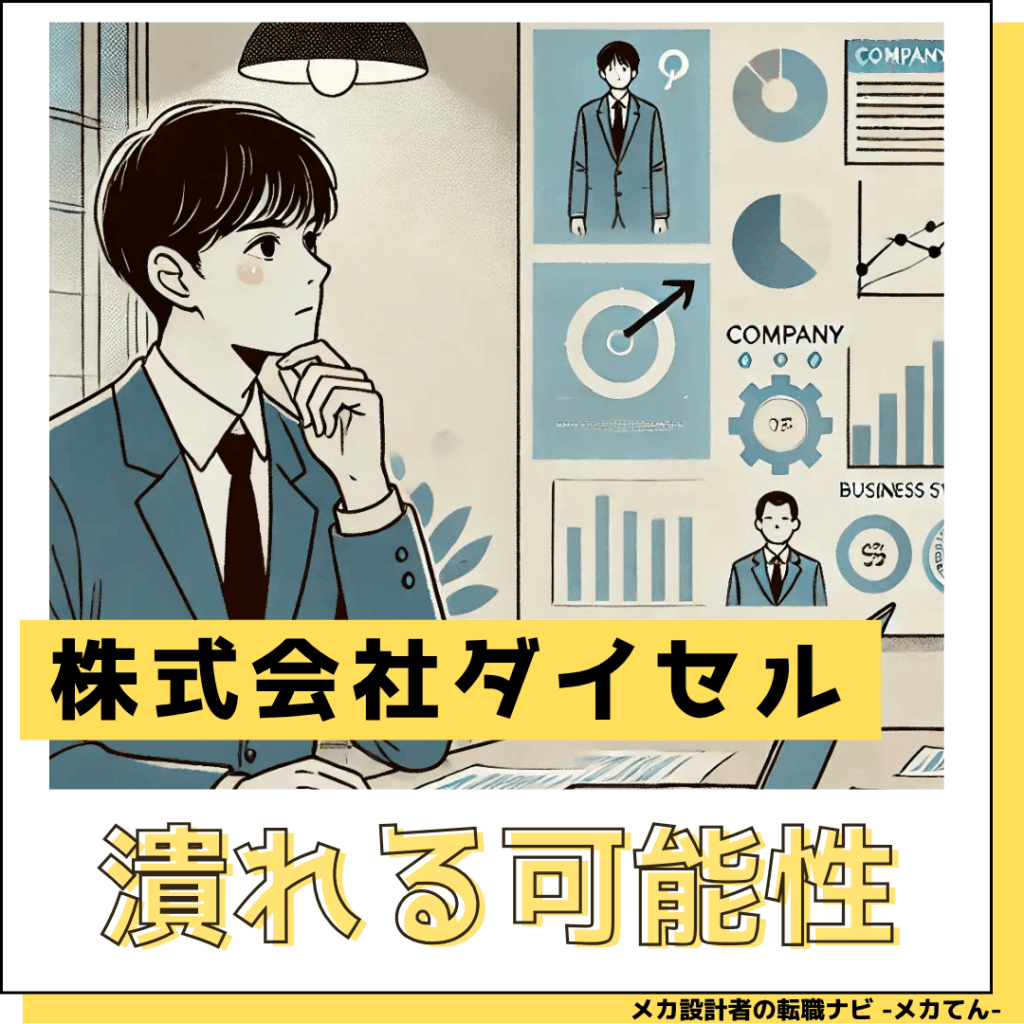
就職や転職活動で企業選びをするうえで、
この会社は将来大丈夫だろうか?
という不安は誰にでもあるものです。
特に、ニュースなどで企業の倒産やリストラが報じられることも多い中で、化学メーカーのダイセルに関しても「潰れないの?」と気になりますよね。
そこでここでは、企業の体力や事業の強みなど多角的な視点から、ダイセルの安定性について掘り下げていきます。
潰れる心配がないといえる根拠は?
まず注目したいのは、ダイセルの「企業規模と収益性」です。
2023年3月期の決算では、売上高は5,400億円を突破し、営業利益は500億円を超えるなど、極めて好調な業績を維持しています。
景気の波に左右されにくい製品群を有しており、たとえば自動車のエアバッグ用ガス発生剤では世界的に高いシェアを誇ります。
これにより、経営の柱がしっかりしていることがわかります。
多角化された事業でリスクを分散
ダイセルは自動車分野だけでなく、電子機器、医療、包装、バイオマスといったさまざまな産業に関わる製品を展開しています。
特に注目されているのが、微細なガラス板を使った「マイクロプラント」技術や、環境対応型素材の研究開発です。
これにより、一つの市場に依存するリスクを避け、外部環境の変化にも柔軟に対応できる体制を整えています。
財務基盤と内部体制の強さ
倒産リスクを考えるうえで、財務面の健全さも重要です。
ダイセルは自己資本比率が高く、キャッシュフローも安定しており、急な経済ショックにも耐えうる体力があります。
また、中期戦略「Accelerate 2025」を通じて、研究開発への投資や、収益構造の見直しを積極的に進めています。
こうした長期的な視野を持った経営方針が、企業の持続性をさらに強固なものにしていると言えるでしょう。
サステナブル経営で社会的信用も高い
近年は「SDGs」や「カーボンニュートラル」といった社会課題への対応も、企業の信頼性を測る指標となっています。
その点でもダイセルは先進的な取り組みを行っており、環境配慮型製品の開発や、エネルギー消費の少ない製造プロセスの構築など、企業の価値を高める努力を継続中です。
社会的責任を果たしながら利益を生み出す体制が整っているのは、安定性を測るうえで重要な要素です。
【総括】就職先・転職先として安心できる企業
株式会社ダイセルは、売上や利益の安定感に加え、技術力、事業の多様性、サステナブルな経営体制を兼ね備えた企業です。
単に「潰れない」と言うよりも、時代の変化に対応し続ける柔軟さと強さを持っていることが大きな魅力といえるでしょう。
今後も成長を続ける可能性が高いため、転職先として安心感のある企業を求める方には十分に検討する価値がある会社です。
強みと将来性を徹底調査
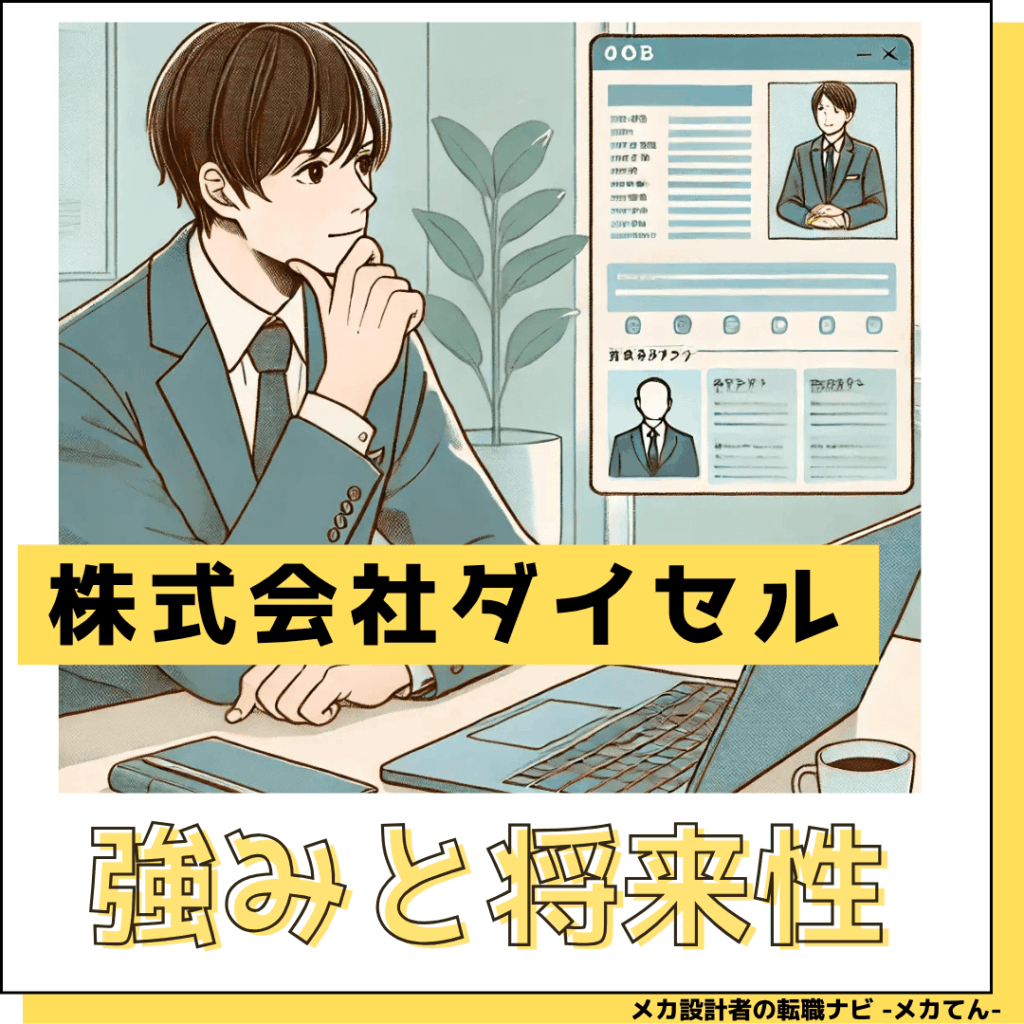
ダイセルへの就職や転職を検討するうえで、
「どんな強みがあるのか?」
「これからも成長する会社なのか?」
という点は非常に気になるポイントです。
ここでは、企業の競争力の源泉と、今後の成長可能性について詳しく見て行きます。
【強み1】世界的シェアを誇る製品群
ダイセルの最も大きな強みは、ニッチでありながら世界的に高いシェアを持つ製品の存在です。
特に有名なのが、自動車向けのエアバッグ用ガス発生剤。
これは、事故の瞬間に瞬時にエアバッグを膨らませるための中核部品で、安全性と安定供給が命です。
ダイセルはこの分野で国内外から高く評価されており、安定した需要が見込まれる分野で確固たる地位を築いています。
【強み2】独自の差別化技術と研究開発力
もうひとつ注目したいのは、「マイクロプラント」や「高機能フィルム」など、他社にはない独自技術の数々。
マイクロプラントは、従来の大規模な化学設備を極小化し、省エネかつ高効率で化学製品を製造できる革新的な仕組み。
これにより、環境負荷を減らしながら製造コストも下げるという、時代にマッチした価値を生み出しています。
さらに、高機能フィルムはスマートフォンや医療機器、自動車などの分野に広く使われ、社会インフラを支える重要な素材となっています。
【強み3】多角的な事業展開とグローバル展開
ダイセルは、1つの分野に依存せず、化学、自動車、電子機器、医療、包装材料など、幅広い分野に事業を展開しています。
このような「多角化」によって、特定の業界の不調があっても全体へのダメージを最小限に抑えられる強みがあります。
また、グローバルにも事業展開しており、アジアや北米を中心に海外売上比率も年々上昇。
国内市場だけでなく、世界中の需要を取り込む体制が整っている点も、将来の安定性を高めています。
【将来性1】「Accelerate 2025」で描く中期ビジョン
将来性という観点では、ダイセルが掲げている中期経営計画「Accelerate 2025」に注目。
これは、環境問題やエネルギー問題といった社会課題に対して、技術で応える姿勢を明確にした戦略です。
具体的には、バイオマス素材の開発、循環型社会への対応、製造工程のデジタル化といった分野に投資を強化しており、持続可能な成長モデルを志向しています。
【将来性2】環境・安全・DXの3本柱で市場に応える
さらに、環境対応技術の開発、安全性の高い製品への需要、そしてDX(デジタルトランスフォーメーション)による生産革新という3つの軸で、時代のニーズにマッチした戦略を展開中です。
特に、データを活用した生産プロセスの最適化や、CO₂削減につながる製品開発などは、企業のブランド力を高める要因にもなっています。
【総括】時代の変化に対応できる「しなやかな強さ」がある企業
ダイセルの強みは、単なる「製品力」や「技術力」だけではありません。
多角的な事業ポートフォリオ、研究開発への継続的な投資、そして社会課題に応える企業姿勢が相まって、時代の変化に柔軟に対応できる強さを持っています。
安定性と将来性を兼ね備えた企業として、安心してキャリアを築ける環境が整っているといえるでしょう。
そもそもダイセルは何の会社?

「名前は聞いたことあるけど、何をしている会社かピンとこない」──ダイセルもそんな会社の1つではないでしょうか。
ここでは、株式会社ダイセルの基礎情報から事業内容、世の中への役割までを丁寧に見て行きます。
化学メーカーとしてのルーツと歴史
ダイセルは1919年創業という、100年以上の歴史を持つ老舗化学メーカーです。
社名の由来は「大日本セルロイド株式会社」からきており、元々はセルロイド製品の製造からスタートしました。
時代とともに技術を進化させ、現在では機能性化学品を中心とする多彩な製品群を展開する総合化学メーカーへと成長を遂げています。
「モノづくり」で社会を支える企業
現在のダイセルは、以下のような分野で活躍しています。
- 自動車安全部品(エアバッグ用ガス発生剤)
- 電子材料(高機能フィルム)
- 医療・ヘルスケア材料
- 包装材・プラスチック製品
- 産業用化学品(有機合成・セルロース誘導体など)
とくにエアバッグ用のガス発生剤は、世界的なシェアを誇る看板製品です。
交通事故の衝撃を和らげる重要パーツとして、自動車メーカー各社から高く評価されています。
また、スマートフォンや医療機器に使われる高機能フィルムの開発にも力を入れており、日々の暮らしのさまざまな場面で、私たちが気づかないうちにダイセルの技術が使われています。
研究開発型企業としての強み
ダイセルの特徴のひとつは、研究開発に注力する「技術志向型企業」であること。
バイオマス素材や再生可能エネルギーの分野、さらには化学反応を小規模化・自動化するマイクロプラント技術など、次世代を見据えたイノベーションに積極的に投資しています。
このような研究開発姿勢は、環境問題や省エネルギーといった社会課題の解決にも直結しており、単なる「化学製品の製造会社」ではなく、「社会貢献型メーカー」としての側面も持ち合わせています。
【総括】暮らしの裏側を支える縁の下の力持ち
一見すると、一般消費者にとってはなじみが薄いかもしれませんが、実はダイセルの製品や技術は、私たちの生活の安全・便利・快適を陰で支えています。
化学を通じて社会と産業に貢献し続ける企業、それが株式会社ダイセルの実像です。
「化学」と聞くと難しく感じるかもしれませんが、ダイセルはまさにその力で未来をつくろうとしている、頼もしい日本発のグローバル企業です。
「しんどい」「やばい」という評判の真相

ネットや口コミサイトなどで、
といったネガティブなワードを見かけたことがある人もいるかもしれません。
こうした声が本当に事実なのか、実際の職場環境や働き方を深掘りして見て行きましょう。
「しんどい」と言われる原因とは?
ダイセルに限らず、製造業や化学メーカーでは、一定の体力的・精神的負荷がかかる業務があるのは事実です。
とくに以下のような理由で「しんどい」と感じる社員がいることは否定できません。
- 工場勤務のシフト制勤務が体にこたえる
- 技術職では高度な専門知識や責任が求められる
- 研究開発では成果へのプレッシャーが大きいこともある
- 部署によっては人手不足を感じる場面もある
ただし、これは職種や配属部署によって大きく異なり、すべての社員が「しんどい」と感じているわけではありません。
働き方改革への取り組みが進行中
「やばい」と言われがちな背景には、かつての長時間労働や残業体質のイメージが残っている可能性もあります。
しかし、近年のダイセルは働き方改革に積極的で、以下のような改善が進められています。
- 残業時間の抑制(平均月20時間以下)
- リモートワークや裁量労働制の導入
- 有給休暇取得の推進
- ワークライフバランス重視の文化づくり
とくに
という口コミも見受けられ、制度としての整備は進んでいるようです。
社内の風通しや人間関係は?
社内文化については
という声が多く見られます。
一方で、
といった声もあるため、上司や部署による差があるのは否めません。
また、新卒よりも中途採用の社員に対しても比較的オープンな社風で、馴染みやすいという評判もあることから、転職組にとっても働きやすい環境を整えつつあります。
ネガティブな噂だけに振り回されないことが大切
確かに「しんどい」「やばい」といった評判が一部に存在するのは事実です。
ただ、それは全体のごく一部の声であり、個人の経験や状況に依存する要素も大きいです。
実際には
というポジティブな評価も増えており、バランスよく情報を見極めることが転職検討者にとって重要です。
【総括】正しい情報で判断しよう
ネット上の噂だけで企業を判断するのは危険です。
ダイセルには確かにハードな面もありますが、それと同時に改革のスピードも速く、環境は年々改善されています。
「しんどい」かどうかは職種や個人の価値観にもよるため、気になる方は実際に社員の声や働き方を詳しく調べ、自分に合うかどうかを見極める視点が大切です。
主な勤務地と転勤頻度
ダイセルへの転職を検討する際、
「どこで働くのか」
「転勤は多いのか」
は非常に気になるポイントではないでしょうか。
勤務地によって働き方や生活スタイルは大きく変わるため、事前にしっかり把握しておくことが大切です。
全国に広がる拠点|主要な勤務地とは?
ダイセルの勤務地は本社を含め、全国各地に複数存在します。
代表的な勤務地は以下のとおりです。
- 本社(大阪):大阪市北区(グランフロント大阪)
- 東京本社:東京都港区(首都圏の営業・企画拠点)
- 名古屋支社:中部エリアの営業・サポート拠点
- イノベーションパーク(兵庫県たつの市):研究開発・生産技術拠点
- 兵庫製造所(網干工場・広畑工場・播磨工場・神崎工場):ダイセルの中核的な製造拠点が集中
- 新井工場(新潟県妙高市)
- 大竹工場(広島県大竹市)
これらの拠点では、それぞれ研究開発・生産・管理・営業などの異なる業務が行われています。
とくに兵庫県には多くの製造所が集結しており、技術職や製造職を希望する場合はこのエリアが主な勤務地となることが多いです。
転勤はあるのか?頻度や傾向を解説
ダイセルでは、職種やキャリアステップによって転勤の有無や頻度が異なります。
営業職や総合職として入社する場合は、全国拠点への異動や転勤の可能性がある一方、工場勤務や専門職(研究・生産技術など)の場合は勤務地がある程度固定される傾向があります。
口コミや社員の声をもとにした転勤傾向の特徴は以下の通りです。
- 技術職(開発・生産系):勤務地は固定される傾向あり。イノベーションパークや各工場勤務が多い。
- 営業・管理職:本社および全国支店への異動があり得る。3〜5年単位でのローテーションも。
- 転勤は少なめだが、ゼロではない:本人の希望やキャリアアップのための異動もある。
また、近年ではダイセル全体としてワークライフバランスの改善や地域密着型の働き方を進めており、必要以上の転勤は避ける傾向にあるようです。
勤務地選びはキャリアにも直結
勤務地は単なる働く場所ではなく、その後のキャリア形成にも影響する要素です。
たとえば、研究開発職であればイノベーションパークや各工場での経験が、将来の技術責任者へのステップに繋がります。
逆に、本社や都市部での業務経験を通して、管理職・企画職へ進む道もあります。
転勤に対する考え方は人それぞれですが、自身の志向に合った勤務地選びが、満足度の高い働き方を実現する鍵になるでしょう。
【総括】希望勤務地と転勤の可能性を確認しよう
ダイセルでは、勤務地ごとに業務の内容や働き方が大きく異なります。
転職時には、自分がどの職種でどの拠点に配属されるのか、転勤の可能性があるのかをしっかり確認することが重要です。
企業としても働き方改革を推進しており、必要以上の転勤を避ける傾向も出てきています。
希望を伝えることで柔軟に対応してくれる場合もあるため、応募前や面接時にしっかり意思を伝えておきましょう。
年収は低いのか?
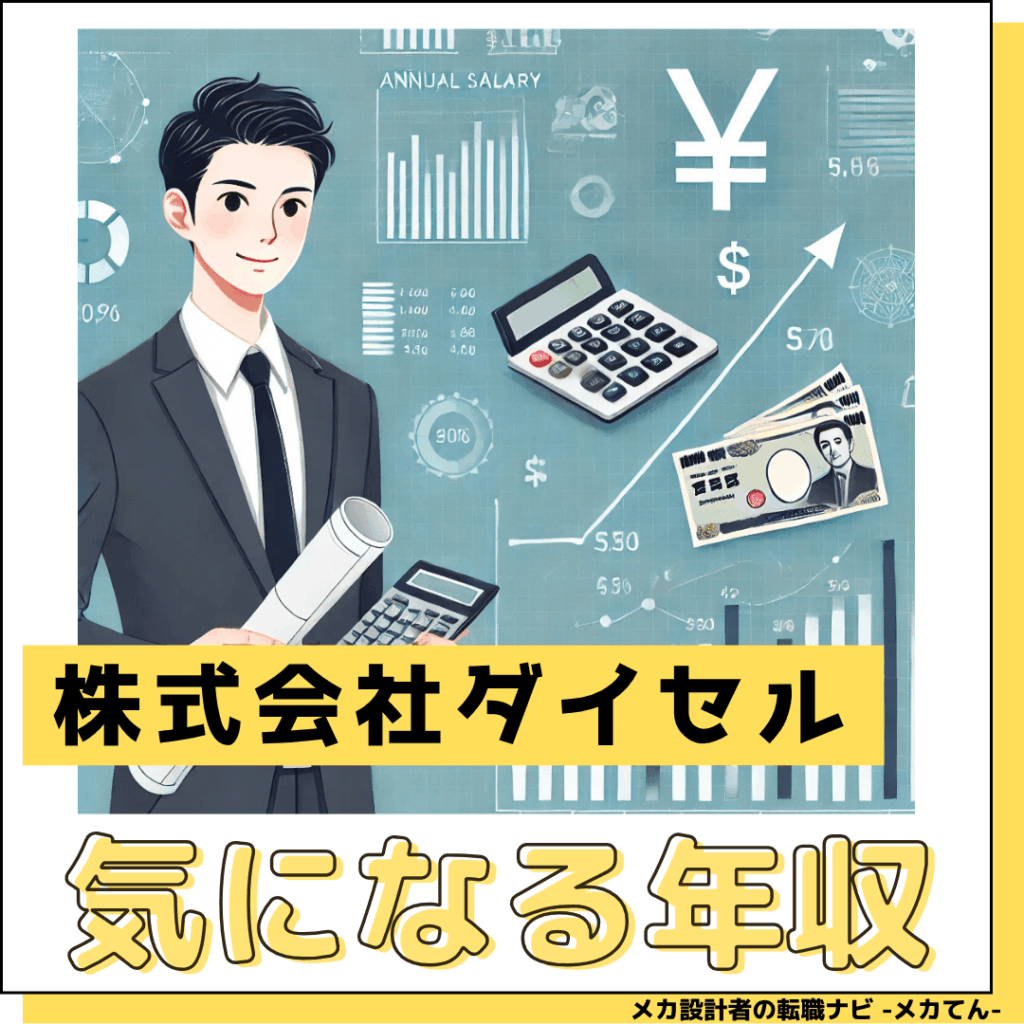
ダイセルへの転職を検討する上で、「年収」は非常に重要な判断材料です。
とくに製造業や化学メーカーという業種柄、給与水準や待遇に不安を感じる人も少なくありません。
ここでは、ダイセルの年収について詳しく見ていきましょう。
平均年収は743万円|業界内でも高水準
直近のデータによると、
とされています。
国税庁が発表している「資本金10億円以上の企業の平均年収(629万円)」と比較しても、ダイセルの給与は平均を大きく上回っており、決して低くはありません。
また、同業他社の大手化学メーカーと比べても、遜色ない給与水準であると言えるでしょう。
初任給も安定している|学歴によって差あり
ダイセルの新卒初任給は以下の通りで、学歴に応じて支給額が明確に定められています。
- 高専卒:190,000円
- 学部卒:220,000円
- 修士了:240,000円
- 博士了:274,300円
特筆すべきは、初任給が高いわけではないが、年次を重ねるごとに昇給が見込める給与体系になっている点です。
これは「年功序列」と「成果主義」のバランスをとっている日本型の企業らしいスタイルとも言えます。
実際の社員の声|残業代や手当はどうか?
口コミサイトや社員レビューによると、基本給に20時間分の残業代が含まれているとのこと。
これを超える分に関しては、しっかりと別途支給されるため、サービス残業のような不安は少ない印象です。
また、以下のような補足的な給与要素もあります。
- 家族手当・住宅手当など福利厚生が充実
- 昇進・昇格に応じた等級制度あり
- 業績によって賞与(ボーナス)も比較的安定
これらを加味すると、
だと評価できます。
ワークライフバランスと年収のバランスも◎
ダイセルは、働き方改革にも積極的で、労働時間は1日7時間30分と他社より短めです。
また、在宅勤務や有給休暇の取得促進にも取り組んでおり、プライベートとの両立がしやすい会社としても評判です。
つまり、年収が高ければいいというより、時間的・精神的な余裕を持ちつつ、安定した収入を得られるという点で、非常にバランスの取れた職場環境が整っています。
【総括】年収は「低くない」どころか、コスパ良好
結論として、ダイセルの年収は決して低いわけではなく、同規模・同業種と比較しても十分に高水準です。
さらに、福利厚生や残業代の支給体制、柔軟な働き方といった要素も加わることで、働きやすさと収入の両立がしやすい企業といえるでしょう。
「収入だけでなく、人生の質も重視したい」と考える方にとっては、魅力的な転職先になり得る会社です。
主な採用大学
就職活動をするうえで、「どの大学から内定が出ているのか」は、企業の選考基準や学歴フィルターの有無を見極める重要なポイントになります。
ダイセルは全国から幅広い大学の学生を採用していますが、ある程度の傾向が見えてきます。
採用実績がある大学|国公立・有名私大が中心
ダイセルが公表している採用実績には、難関国公立から中堅私大まで幅広い大学が含まれています。
以下はその一部です。
<主な国公立大学>
- 大阪大学
- 東北大学
- 名古屋大学
- 北海道大学
- 東京工業大学
- 九州工業大学
- 岡山大学
- 熊本大学
- 金沢大学 など
<主な私立大学>
- 早稲田大学
- 慶應義塾大学
- 上智大学
- 明治大学
- 立教大学
- 同志社大学
- 関西学院大学
- 芝浦工業大学
- 東京理科大学 など
これを見ると、旧帝大や地方の国公立大学、理工系に強い私立大学からの採用が目立ちます。
理系出身者の比率が高い
ダイセルは化学メーカーであり、研究開発や生産技術など理系職種の比重が大きいため、理工系の学部出身者が多数を占めています。
技術系の採用では、大学での研究内容や論理的思考力、実験スキルなどが重視される傾向があります。
一方、事務系職種では文系学生の採用も一定数ありますが、こちらも一定以上の学力が求められる傾向がありそうです。
学歴フィルターはあるのか?
採用実績を見る限り、「学歴フィルター」が完全に存在しないとは言い切れません。
ただし、全国の幅広い大学からの採用があるため、偏差値だけで足切りをしているような印象は薄いです。
重要なのは、大学名以上に「面接での受け答え」や「自分の強みをどう伝えるか」といった総合力。
中には地方大学出身でも、研究内容や人柄を評価されて内定を勝ち取っているケースもあります。
【総括】偏差値だけでなく人物も重視する企業
ダイセルは、難関大学からの採用実績が多い一方で、中堅大学や地方大学の学生にも門戸を開いている企業です。
理系出身者が中心となるものの、文系職種も一定数存在し、自分の強みを活かして挑戦できる環境が整っています。
「有名大学じゃないと無理かな…」と不安な方も、しっかりと準備をすれば十分チャンスがあります。
学歴だけで判断せず、企業研究や自己分析を深めて臨むことが内定への近道です。