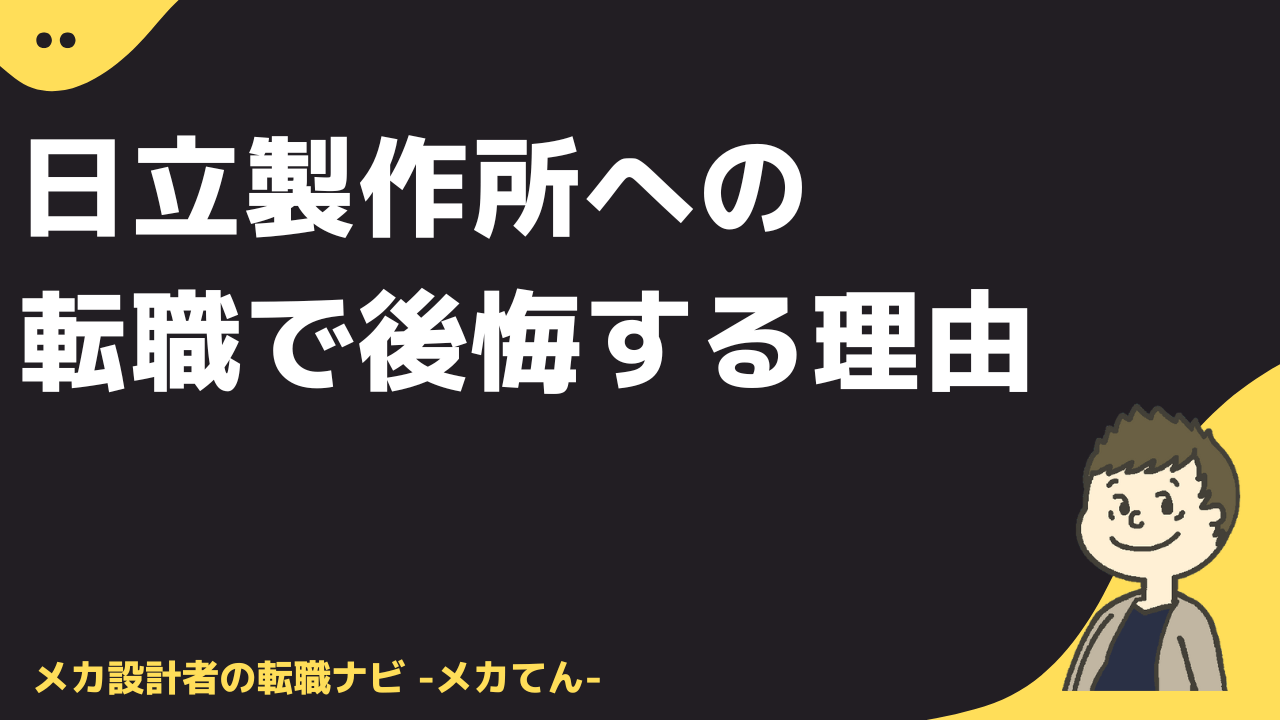日立製作所への転職は、「やめとけ」と言われるほど覚悟が必要です。
ただし、条件が合えばキャリアアップのチャンスにもなり得ます。
この記事では、日立製作所へ転職して後悔した理由や「やめとけ」と言われる背景をはじめ、中途採用でも出世できるのか、難易度や人気部署の情報まで網羅的に見て行きます。
「転職先として日立はどうなのか?」と迷っている方は、ぜひ最後まで読んで判断材料にしてください。
日立製作所への転職で後悔する理由
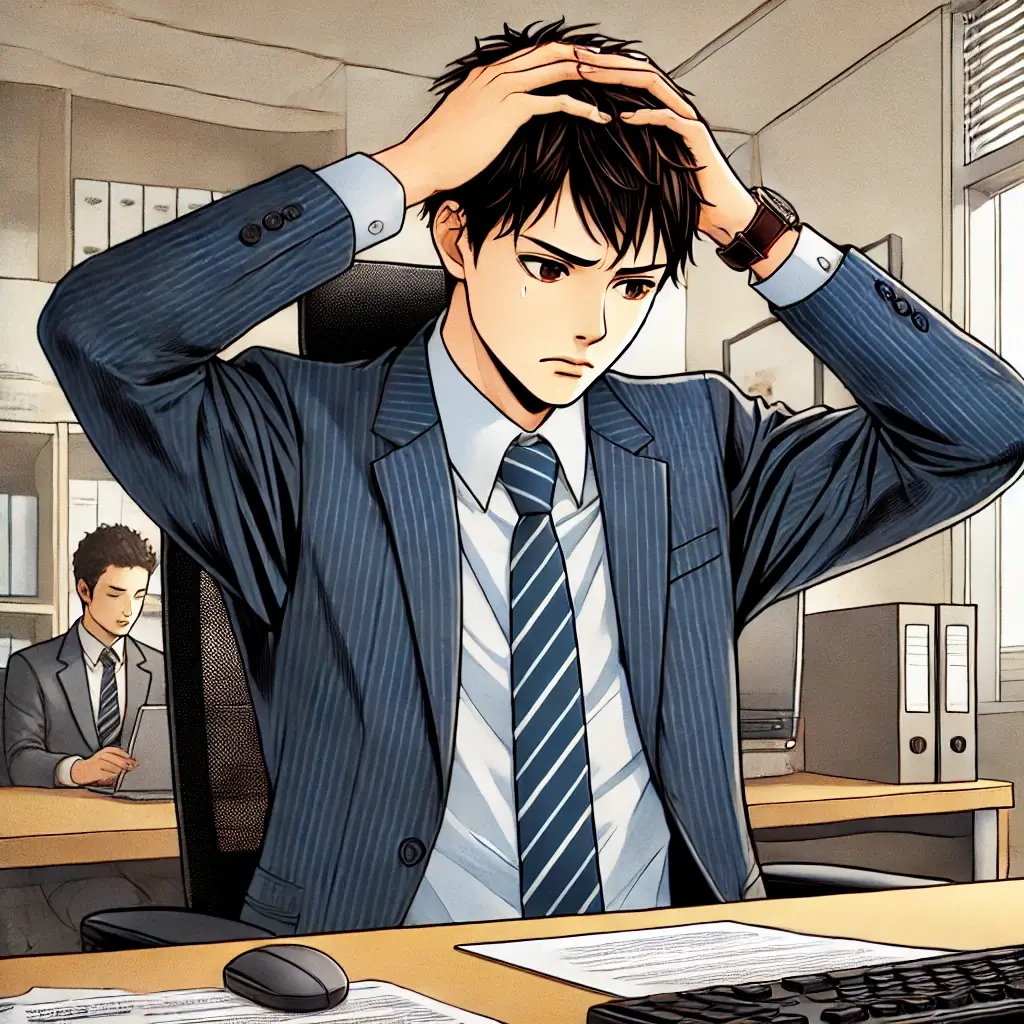
転職先としての安定感やネームバリューのある日立製作所ですが、実際に入社してみて「思っていたのと違った」と感じる人もいます。
ここでは、転職後に後悔しやすいポイントを深掘りしながら、なぜそう感じるのかを丁寧に解説していきます。
成果より年次が優先される評価制度
日立製作所は伝統的な日本企業の中でも、特に年功序列の文化が根強く残る企業です。
たとえ即戦力としてスキルや経験が豊富でも、年次が若いと正当な評価を得にくい場面があります。
特に中途入社の場合、いくら成果を出しても評価や昇格のスピードが新卒入社組よりも遅れると感じる人も少なくありません。
これは、制度上では実力主義を掲げていても、実際の現場では“社歴”がモノを言う場面が多いためです。
「前職ではリーダーを任されていたのに、ここでは意見が通らない」といったギャップに悩む人も見受けられます。
意思決定が遅く、スピード感に欠ける
もう一つの大きな壁が、業務のスピード感の違いです。
日立製作所は大企業ゆえに関係部署が多く、何を進めるにも稟議や調整が必要なケースが多くあります。
特に外資系やベンチャーなど、スピード感を持って意思決定が行われていた企業からの転職者にとっては、一つのプロジェクトを進めるだけでも煩雑なプロセスがストレスになることがあります。
「良かれと思って提案しても、通るまでに数カ月かかる」といった声もあります。
部署によって差が激しい仕事のやりがいと裁量権
日立は事業領域が広く、部署ごとに業務内容や雰囲気が大きく異なります。
そのため、どの部署に配属されるかによって、感じるやりがいや成長実感に大きな差が出ることがあります。
とくに保守的な部署に配属された場合は、
など、仕事への熱量を失ってしまう人も。
中には、前職で感じていた裁量の大きさとのギャップに悩み、転職自体を後悔する人もいるようです。
中途入社者にとってのキャリアの壁
出世を目指す人にとっては、中途入社という立場自体がハンデになるケースもあります。
日立製作所では、若手のうちから「幹部候補」として社内育成される人材が存在し、そうした社員と競う形になるため、どうしてもポジション獲得が難しくなることがあります。
社内での信用や人脈も重要視されるため、転職してすぐに結果を出しても、「本当の意味での昇進」は数年後になることが多いのです。
大企業ならではの“安定感”が裏目に出ることも
「安定していて安心」と思って入社する人も多い日立製作所ですが、裏を返せば変化を嫌う体質ともいえます。
そのため、
というタイプの人ほど、企業文化と合わずに後悔しやすい傾向があります。
また、安定志向が強いため、新しい提案や挑戦が通りにくい環境にフラストレーションを感じる人もいます。
転職前に必要なのは「企業文化への理解」
日立製作所への転職を後悔する人の多くは、企業の内側にある文化や体質を知らずに入社してしまったケースです。
ネームバリューや待遇面の魅力だけで判断せず、自分が本当にフィットする環境かどうかを見極めることが非常に大切です。
とくに中途採用の場合、「即戦力として求められる」一方で、「新卒組とは異なるルート」でのキャリア形成になるため、そこに生じるギャップをしっかり想定しておく必要があります。
【総括】安定の裏にある「変わりにくさ」をどう捉えるか
日立製作所は確かに安定感があり、働きやすさも整備された企業です。
しかし、その一方で「動きにくさ」や「年功序列」といった特徴も抱えています。
これらを踏まえて、自分のキャリアの価値観と照らし合わせた上で、後悔のない転職判断を行うことが重要です。
やめとけと言われる背景
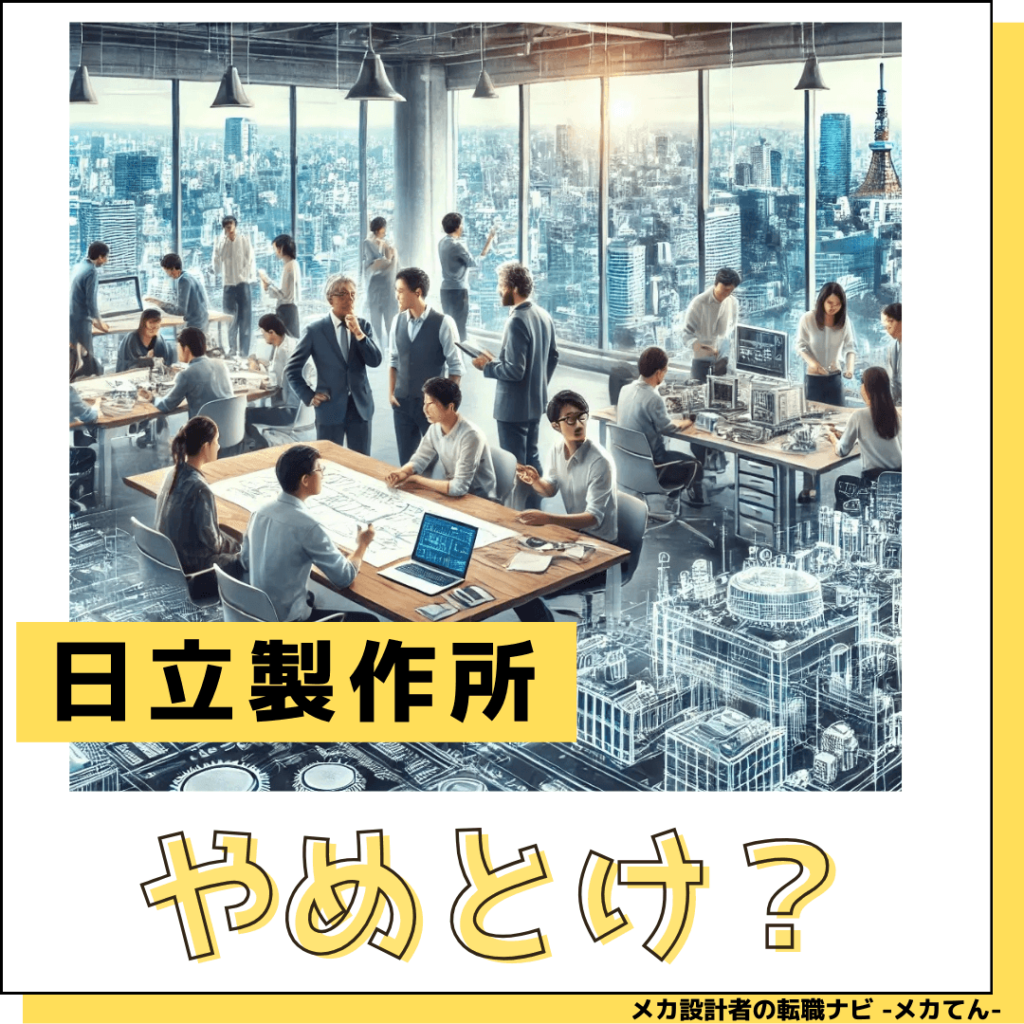
日立製作所への転職を検討していると、ネット上や転職経験者の声の中に「やめとけ」という意見が目に留まることがあります。
なぜそのようなネガティブな声が出るのでしょうか?
背景には、表面上の情報では見えにくい実情や、働く人によって感じるギャップが存在します。
ここでは、そうした「やめとけ」と言われる理由を掘り下げていきます。
「大企業=安泰」のイメージとのギャップ
日立製作所は、日本を代表する大企業として知られ、グローバルでも高い知名度を持っています。
しかし、そのブランド力ゆえに、実態以上の期待感を抱いてしまう人も少なくありません。
「大企業だから、働きやすくて、成長もできるはず」といった期待を持って転職したものの、実際はルールや縦割り構造に縛られ、自由度が低いと感じるケースが多いのです。
こうした現実とのギャップが、「こんなはずじゃなかった」という声につながり、結果的に「やめとけ」という意見が出る背景になっています。
変化が遅く、保守的な風土
日立製作所の企業文化には、変化よりも安定を重視する姿勢が色濃く残っています。
たとえば新しいプロジェクトや業務改善提案をしても、すぐに採用されるとは限らず、稟議を経て何カ月もかかることは珍しくありません。
こうした保守的な社風は、スピード感や挑戦を求める人にとっては大きなストレスとなります。
特にベンチャー企業や成果主義の企業で働いていた人が転職した場合、「なぜこんなに動きが遅いのか」とフラストレーションを抱えがちです。
中途採用者が感じやすい“壁”
日立では年功序列や社内人脈が重要視される傾向があり、中途採用者が影響力を持つまでには時間がかかります。
特に意思決定の場や大きなプロジェクトには、長年社内でキャリアを積んだ社員が起用されやすい傾向にあります。
中途入社者は、どうしても「よそ者」として見られがちで、社内の空気感や暗黙の了解をつかむまでに苦労することも。
という声が、やめとけと言われる背景につながっています。
残業や業務量が部署によって大きく異なる
「やめとけ」と言われるもう一つの理由が、部署ごとの働き方のばらつきの大きさです。
たとえば、IT系やインフラ系の部門では深夜や休日の対応が発生するケースもあり、ワークライフバランスが取りにくい環境にあることがあります。
一方で、管理部門や一部のバックオフィス系部署では比較的落ち着いて働ける場合もあり、転職先としての満足度に大きな差が出るのです。
この「部署ガチャ」とも呼べる不確実性が、転職リスクとして語られ、「やめとけ」の根拠の一つになっています。
ネット上の評判とのギャップ
転職前に口コミサイトなどで企業評価を調べる人も多いですが、日立製作所は知名度が高い分、情報が多く、真偽の判断が難しいのも事実です。
ポジティブな意見もあれば、ネガティブな声も同じくらい見つかります。
中には、「こんなに悪いわけがない」と思って入社したものの、実際にはその通りだったというケースも少なくないのです。
ネットの評判を単なる噂として流さず、「なぜそのような声が出ているのか?」を冷静に分析する視点が必要です。
「やめとけ」は一部の声であり、全体像ではない
ここまで紹介したように、「やめとけ」と言われる背景にはいくつかの要因がありますが、すべての人に当てはまるわけではありません。
保守的な風土が合う人にとっては、日立のような環境はむしろ働きやすいと感じるはずです。
問題は、自分の価値観やキャリアの方向性と企業文化がマッチしているかどうか。
転職において大切なのは、「他人の評価」ではなく、「自分に合っているか」という視点です。
【総括】なぜ「やめとけ」と言われるのかを自分なりに理解することが大切
「やめとけ」という言葉に惑わされる必要はありません。
ただし、そう言われる背景には、実際にミスマッチを経験した人たちのリアルな声があることも事実です。
大切なのは、その声を鵜呑みにするのではなく、自分にとって重要な働き方や価値観と照らし合わせて判断することです。
転職は情報戦。
正しい情報をもとに冷静な判断を下すことが、後悔しない転職への第一歩となります。
中途でも出世コースに乗れる?
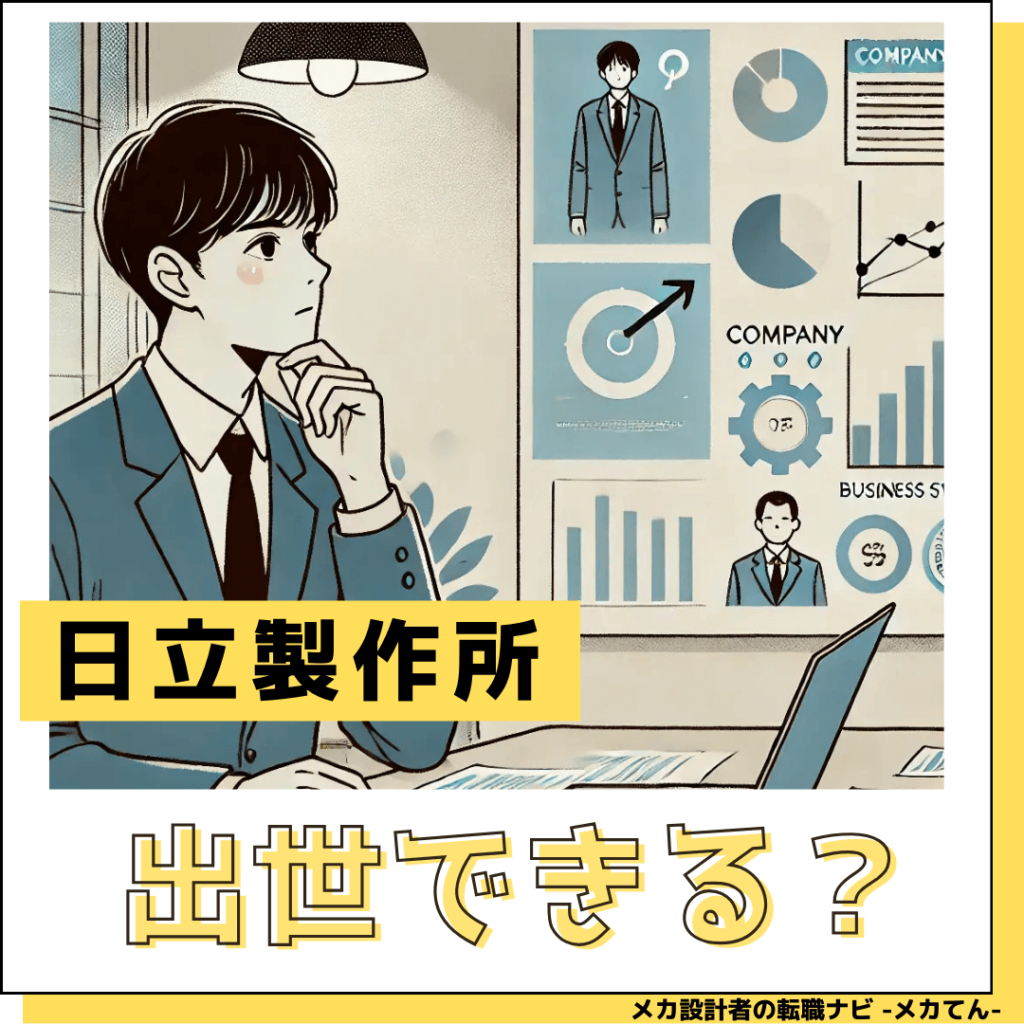
日立製作所のような伝統ある大企業では、「中途採用=補助的な立ち位置」と思われがちです。
では実際のところ、中途入社でも出世コースに乗ることは可能なのでしょうか?
結論から言えば、「不可能ではないが、ハードルは高い」です。
その背景や実情を詳しく見ていきましょう。
新卒優遇のカルチャーは根強い
日立製作所は「終身雇用」「年功序列」といった日本的な雇用慣行を長年維持してきた企業です。
そのため、今でも新卒で入社して社内文化に慣れた人材が評価されやすい土壌が残っています。
昇進・昇格のタイミングも、入社年次に応じたペースで進むことが一般的で、途中から加わる中途採用者にとっては、そのレールに乗るまでに時間がかかる傾向があります。
特に本社勤務やマネジメント職を目指す場合、内部人脈や社内の“空気の読み方”が重要とされるため、出世において不利に働くことがあるのです。
中途でも出世している人はいる
とはいえ、中途採用者がすべて冷遇されるわけではありません。
近年、日立製作所ではグローバル戦略やDX(デジタルトランスフォーメーション)に注力しており、外部からの専門人材を積極的に登用する動きも見られます。
たとえば、IT・デジタル部門、海外事業戦略、人材開発や新規事業創出の分野では、専門性の高い中途入社者がプロジェクトの中心を担い、マネージャーや部長職に昇進している例も存在します。
特に外資系やコンサル出身で、即戦力として実績を出せる人材は、キャリアアップのスピードも早いです。
出世のカギは「社内適応力」と「成果の見せ方」
中途で出世コースに乗るためには、単にスキルが高いだけでは不十分です。
日立のような大企業では、成果主義も取り入れつつあるとはいえ、依然として「協調性」「社内調整力」が評価の対象になります。
特に大きなプロジェクトでは、関係部署との調整や、社内の稟議プロセスを円滑に進めるスキルが必要とされます。
このとき、「外から来た人」ではなく、「社内文化を理解しつつ結果も出せる人材」であることが重要です。
また、評価制度の特徴として「目に見える成果を定量的に示す」ことが求められるため、数字やKPIでのアピール力も出世を左右するポイントとなります。
昇進のスピードには個人差あり
中途入社者の中でも、「5年以内に管理職になれた人」と「10年以上経っても役職なしの人」がいます。
この差を生むのは、“どこに配属されたか”と“どれだけ早く成果を出せたか”にかかっています。
新規事業や重要プロジェクトのある部署に配属されれば、社内外へのインパクトも大きく、上層部の目に留まりやすいですが、ルーチン業務中心の部署では出世のチャンス自体が少ないという現実もあります。
【総括】可能性はあるが「戦略と順応」がカギ
中途でも日立製作所で出世することは確かに可能です。
ただし、それには社内文化への適応、周囲との関係構築、そして成果の可視化という複数の要素が必要となります。
“専門性×社内適応力”を両立できる人材こそが、出世コースに乗れるタイプだと言えるでしょう。
また、自分のスキルが活かされやすい部署に入れるかどうかも成功の鍵を握ります。
希望するキャリアを実現するためには、転職前に配属部門の情報やキャリアパスの事例を入念に確認することが大切です。
中途採用の難易度は難しい?

日立製作所への中途入社を目指すにあたり、最初に気になるのが「そもそも採用されるのは難しいのか?」という点です。
結論から言えば、難易度はやや高め。
特にポジションや職種によっては、高度な専門性や実務経験が強く求められるため、準備不足の状態では突破は難しいでしょう。
採用基準は「即戦力」かどうか
日立製作所の中途採用では、新卒とは違い「ポテンシャル」よりも「即戦力」としての能力が重視されます。
具体的には以下のような基準が設けられる傾向があります。
- 業界経験または職種経験が3~5年以上ある
- プロジェクトマネジメントやリーダー経験がある
- 英語力(TOEIC700点以上など)を活かした業務経験がある
- 特定の専門分野(IT、電機、製造、経営企画など)に関する深い知見がある
特に技術系やIT系、海外事業関連では専門性が評価されやすく、逆に事務系や一般管理部門では競争率が高くなりやすいため、よりハードルが上がります。
転職サイト経由よりも「直接応募」「リファラル」が有利?
求人の出し方にも特徴があります。日立製作所では、転職サイトや転職エージェントを通じて広く人材を募集することもありますが、幹部候補や高度専門職に関しては「リファラル(社員紹介)」や「ダイレクトリクルーティング」経由で採用されるケースが多いのも事実です。
そのため、業界内での人脈やLinkedInなどを活用したネットワーキングも、応募前の重要な戦略になります。
面接は「ロジック」と「カルチャーフィット」の両立がカギ
選考過程では、書類審査の時点でかなり絞り込まれる傾向があります。
書類通過後の面接は、一般的に2〜3回行われますが、その中で特に見られるのは以下の2点です。
- 論理的な思考力・問題解決力(特にコンサル出身の人などはここで強みを発揮)
- 日立の社風やバリューへの理解とフィット感(真面目さ・調整力・協調性)
いくら優秀でも、チームやプロジェクトの中で浮いてしまう可能性がある人材は敬遠される傾向があります。
日立は大企業でありながら慎重な人材選考を行っており、「優秀」だけでなく「組織に馴染めそうかどうか」も重視されるのです。
「採用枠が狭い=倍率が高い」構図も
全体として中途採用の数は新卒に比べてまだまだ少数です。
採用されるポジションは限定的であり、部署ごとの欠員補充や新規プロジェクトの発足時に限られることが多いです。
つまり、チャンスはあるが常時開かれているわけではないという点が、難易度を高める要因になっています。
また、有名企業というブランド力もあり、応募者の質が高く、自然と倍率も上がるため、「誰でも受かる」というわけにはいきません。
【総括】難易度は高めだが、戦略次第で突破可能
日立製作所の中途採用は、全体として「簡単ではない」と言えます。
ただし、それは「自分の強みや専門性をうまく伝えられない場合」に限った話です。
採用の難易度を乗り越えるためには、
- 自分のキャリアの棚卸しと強みの明確化
- 企業研究を通じた「カルチャーとの一致」のアピール
- リファラルやスカウトなど、応募経路の工夫
が欠かせません。
裏を返せば、事前準備をしっかり整えたうえでのアプローチをすれば、中途でも十分にチャンスはあるということ。
転職市場全体が即戦力重視にシフトしている今、日立製作所も例外ではありません。
タイミングと戦略を見極めて、自分の強みを最大限に活かしましょう。
気になる離職率

日立製作所のような大企業で働くとなると、給与や待遇だけでなく「人がどのくらい辞めているのか=離職率」も非常に気になるポイントです。
いくら条件が良くても、人がどんどん辞めていく職場では安心して長く働くことはできません。
結論から言えば、日立製作所の離職率はかなり低めで、安定した職場環境といえます。
ただし、それが「すべての人にとって快適」かというと、事情はもう少し複雑です。
平均離職率は約2〜3%前後とかなり低め
日立製作所の離職率は、直近の公表データや就職四季報などの各種資料を見る限り、2〜3%前後で推移しています。
これは日本の民間企業の平均離職率(約15%前後)と比べても、圧倒的に低い数値です。
特に新卒3年以内の離職率も10%未満とされており、若手の定着率も非常に高い水準。
長期的に働く前提で採用・育成される企業文化が根付いていることがわかります。
離職率が低い理由:安定性と待遇の良さ
このように離職率が低い背景には、いくつかの大きな理由があります。
- 年功序列・終身雇用に近い体制:急激な成果主義ではなく、着実にキャリアを積む文化が根強い
- 福利厚生の充実:社宅、持株制度、住宅手当、各種保険制度など大企業ならではの手厚さ
- 残業・労務管理が比較的しっかりしている:部署による差はあるものの、法令遵守意識は高め
- 辞めるリスクが大きいと感じる社員が多い:特に中高年層は他社への転職が難しいため、現職にとどまる傾向が強い
つまり、安定志向の人にとっては非常に居心地が良い環境だと言えます。
ただし、「居心地の良さ=やりがい」ではない
一方で、離職率が低いことが「誰にとっても働きやすい」ことの証明かというと、必ずしもそうとは限りません。
実際には以下のような声も見られます。
- 「変化が遅く、意思決定に時間がかかる」
- 「上司の顔色を見ながら動くのが疲れる」
- 「年功序列が強く、成果が評価されにくい」
- 「転職で入った人は出世に時間がかかる」
このように、チャレンジ志向の強い人やスピード感のある成長を求める人にとっては、むしろ窮屈に感じる場合もあるのです。
離職率が低いという事実の裏には、「定着率が高い=不満があっても辞めにくい」構造が存在しているとも言えます。
離職率が低い=ホワイト企業、とは限らない
日立製作所の離職率の低さは、一般的にはポジティブな評価につながりますが、すべての人にとって「働きやすい職場」とは限らないことを押さえておく必要があります。
特に中途入社で「スピード感のある環境でバリバリ働きたい」という志向を持つ人にとっては、カルチャーギャップを感じる可能性があるため、事前に社風や配属部署の情報をしっかりと確認することが重要です。
【総括】安定志向には最適。ただし人によって合う・合わないがある
日立製作所の離職率は、業界内でもかなり低く、安定性の高い企業といえます。
福利厚生や制度面の整備もあり、安心して長く働ける職場環境が整っています。
ただし、「低離職率=働きやすさの絶対指標」ではなく、社風や働き方が自分に合っているかどうかも重要です。
特に中途での転職を考えている方は、「自分が何を大切にして働きたいか」を明確にし、入社後のギャップを減らす工夫をしておきましょう。
人気の花形部署はどこ?
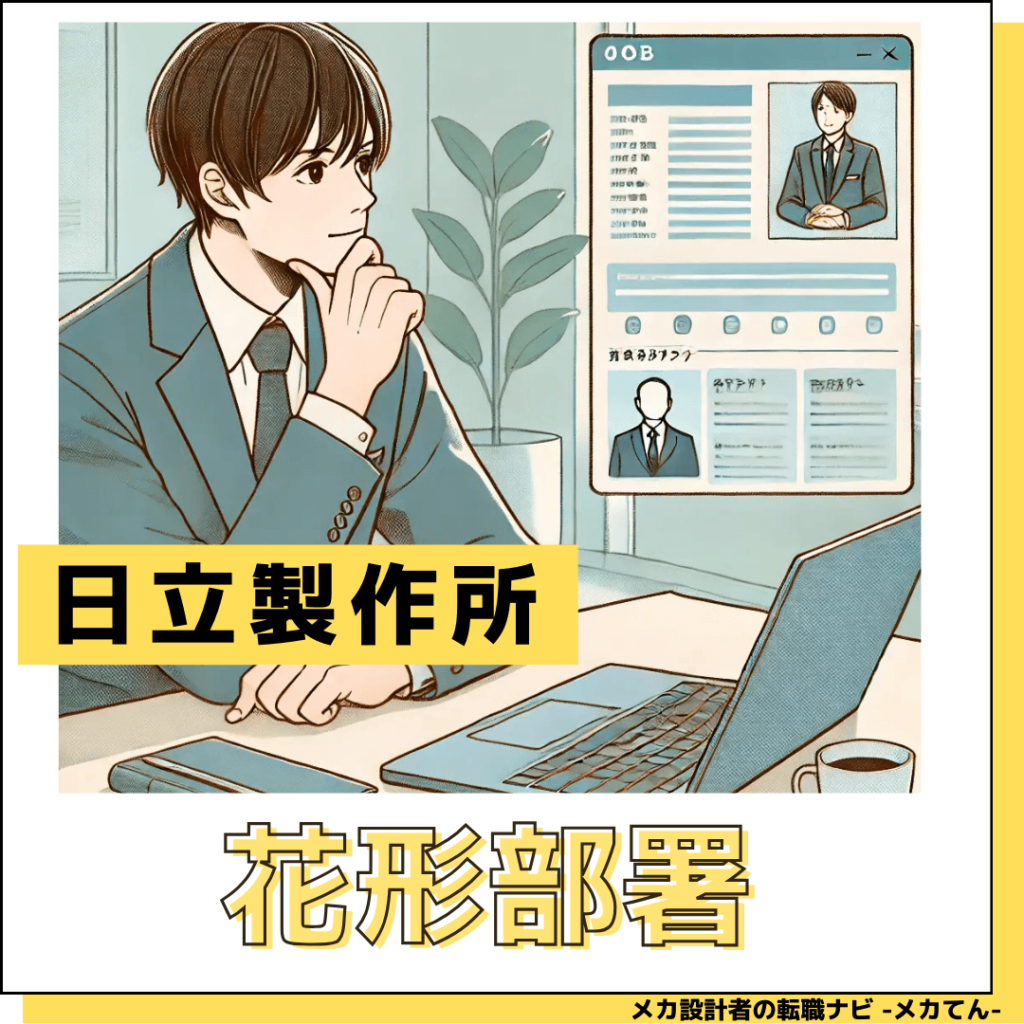
日立製作所は幅広い事業領域を持つ総合電機メーカーであり、技術系から営業、企画、管理部門まで多彩な部署が存在します。
その中でも「花形部署」と呼ばれ、社員の間でも人気・注目度が高いポジションがいくつかあります。
結論としては、
また、グローバル戦略や経営企画部門なども、ハイキャリア志向の人からは人気です。
Lumada事業:日立の次世代エース
「Lumada(ルマーダ)」とは、日立が展開しているIoT・AI・ビッグデータ解析を活用したデジタルソリューション事業です。
たとえば、
- 企業の工場の稼働効率をデータで最適化
- インフラ設備の故障を予測して保守を効率化
- 医療や交通、物流のDX(デジタルトランスフォーメーション)
といったプロジェクトが展開されており、製品単体ではなく、ITを活用した「ソリューション提案型ビジネス」が中心です。
この分野は日立が今後の成長を最も期待している領域であり、人材投資も積極的に行われていることから、社内でも注目度が非常に高い部署です。
海外企業との協業やM&Aも盛んで、グローバルに活躍したい人にとっても魅力があります。
社会イノベーション事業:公共・インフラを支える
もう一つの花形が、「社会イノベーション事業」です。
こちらは、
- 鉄道
- エネルギー
- 都市インフラ(スマートシティなど)
といった分野において、社会の基盤となる大規模プロジェクトに携わる部署です。
たとえば、日立製作所は鉄道システムでイギリスなど海外への展開も行っており、都市ごとの交通や電力ネットワークの最適化など、国家規模のプロジェクトに関われるチャンスがあります。
スケールが大きく、長期的な視点が求められるため、技術力とマネジメント能力の両方が必要になりますが、エンジニア・企画職ともに人気の高いフィールドです。
経営企画・グローバル戦略部門も人気
また、キャリア志向が強い人材から人気が高いのが、経営企画室やグローバル戦略関連の部署です。
ここでは全社戦略の策定や、M&A、子会社・海外拠点の経営支援など、企業の「頭脳」として動くポジションとなります。
外資系コンサルや総合商社出身者も転職してくることがあり、中途採用でも高いスキルや語学力、交渉力を求められる難関ポジションですが、やりがい・裁量の大きさは抜群です。
逆にあまり人気がない部署とは?
一方で、以下のような部署は相対的に人気が低い傾向にあります。
- 間接部門のルーチンワーク系(総務、庶務)
- 古い体質の製造部門(旧来の生産工場など)
- 人事制度や待遇が変わりにくい管理系部署
これらは安定性はあるものの、「変化が少なく、キャリアの展望が見えづらい」として、若手や中途社員からの志望度はやや低めです。
【総括】DX・社会インフラ・経営戦略が三大人気
日立製作所における人気の花形部署は、
- 「Lumadaを中心としたDX関連」
- 「社会インフラ・交通エネルギー系」
- 「経営戦略・グローバル部門」
の3つが中心です。
いずれも大規模かつ未来志向のプロジェクトが多く、キャリア形成の面でもプラスになります。
ただし、競争も激しいため、転職を目指す場合は、自分のスキルや志向と照らし合わせて準備することが不可欠です。
どの部署を目指すにせよ、日立の「全体像」と「自分に合う文化」を理解しておくことで、より良い転職判断ができるでしょう。