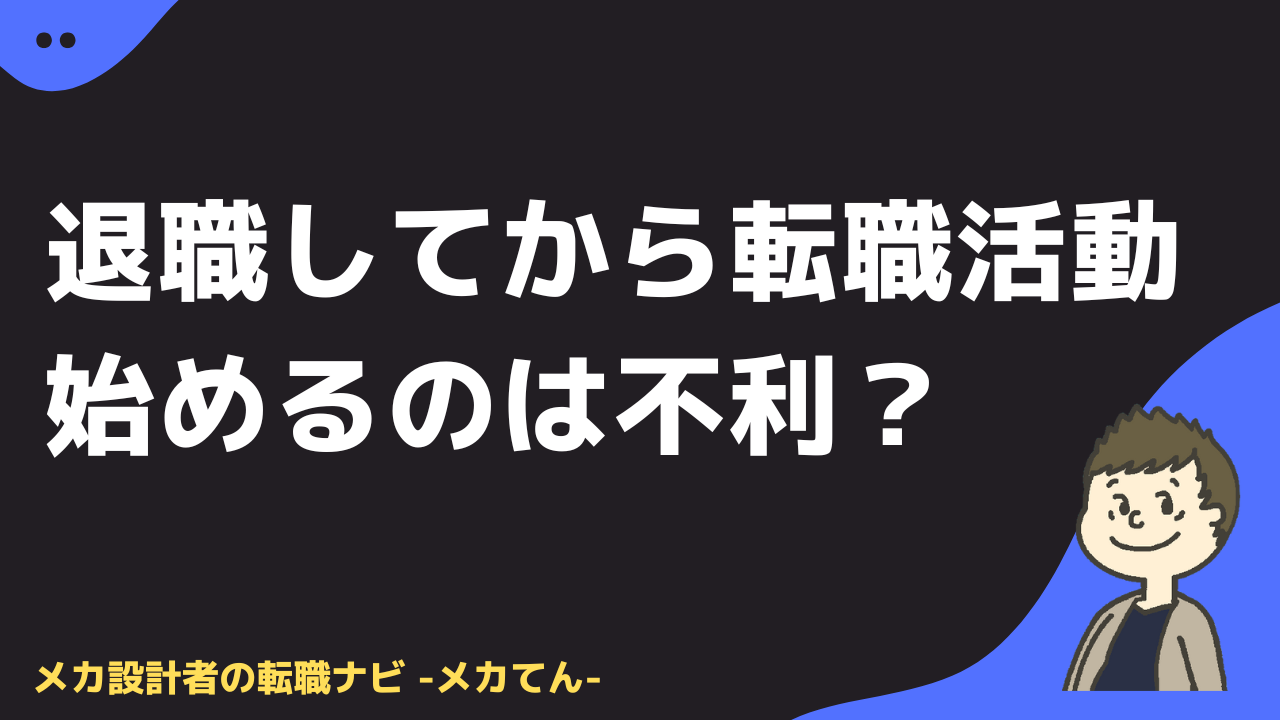退職してから転職活動を始めると、不利になることがあります。
無職の期間が長引くと、採用担当者に「なぜ決まっていないのか?」と思われるからです。
一方で、働きながらの転職活動は時間的な制約があり大変。
どちらが自分に合っているのか、メリット・デメリットを比較しながら、成功のコツを確認して行きましょう。
退職してから転職活動始めるのは本当に不利なのか?
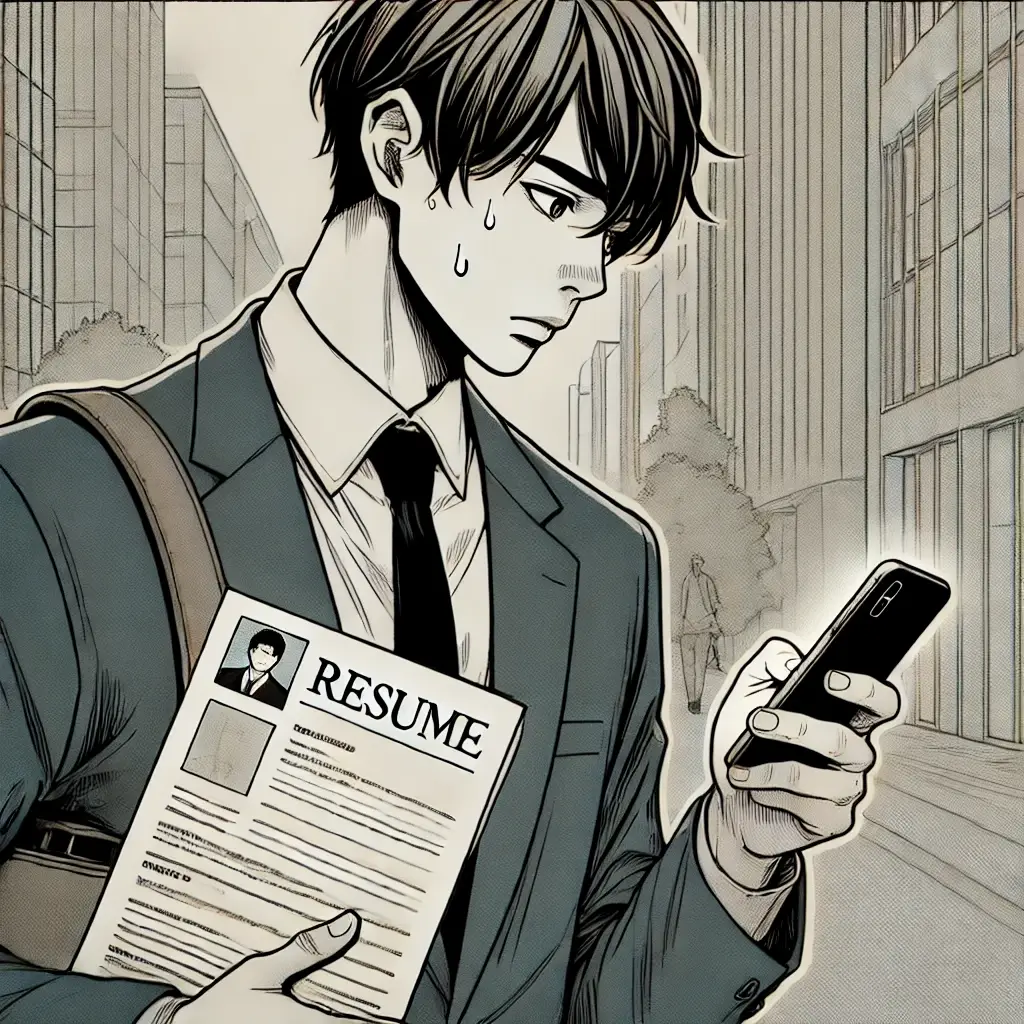
転職を考えているものの、今の仕事を辞めてから活動を始めるべきか、それとも働きながら進めるべきか迷っていませんか?
と言われることもありますが、実際のところはどうなのでしょうか?
結論として、退職してからの転職活動は慎重に進める必要があります。
なぜなら、企業側が「ブランク期間」をどう見るかが重要なポイントになるからです。
転職市場では、安定して働いている人の方が評価されやすい傾向があります。
では、退職後に転職活動を始めることがなぜ不利になりやすいのか、その理由を詳しく見て行きましょう。
転職活動の長期化で不利になる可能性がある
退職後の転職活動は、予想以上に時間がかかることがあります。
理想の企業がすぐに見つかるとは限らず、求人のタイミングによっては、思うように応募できない期間が生じることも。
その結果、転職活動が長引くと
なぜ仕事が決まらないのか?
という疑念を持たれやすくなります。
特に、半年以上のブランクができると、採用担当者は「仕事への意欲が低いのでは?」とネガティブに捉えることがあります。
また、転職市場は時期によって活発な時とそうでない時があります。
求人が増える時期(例えば年度末や上半期のスタート時期)にスムーズに転職できれば問題ありませんが、そうでない場合は思った以上に時間がかかり、経済的な不安が生じることもあります。
経済的な焦りが転職の選択肢を狭める
仕事を辞めてしまうと、当然ながら収入が途絶えます。
貯金が十分にあれば問題ありませんが、そうでない場合、生活費を考えて早く内定を得たいという気持ちが強くなり、結果的に
という状況に陥りがちです。
特に、40代以降の転職では、収入の安定性が重要になります。
家庭を持っている場合、家族を養う責任があるため、経済的なプレッシャーはさらに大きくなるでしょう。
焦って転職を決めてしまうと、
「入社してみたら思っていた環境と違った」
「給与が下がって生活が厳しくなった」
といったミスマッチが起こりやすくなります。
企業がブランク期間をマイナス評価することも
企業側は、応募者の職歴を重視します。
特に即戦力を求める企業では、直近の職歴が重要視される傾向があり、ブランク期間があると
と疑問を持たれやすくなります。
もちろん、
「スキルアップのために資格取得をしていた」
「家族の介護のために一時的に休職していた」
など、明確な理由があれば問題にはなりにくいですが、特に何もしていない場合は
「仕事のモチベーションが低い」
「キャリアプランが曖昧」
と判断されることもあります。
また、企業によっては「仕事をしながら転職活動をしている人=計画的にキャリアを考えている」と評価する傾向もあります。
そのため、退職後に転職活動をする場合は、ブランク期間について納得できる説明を用意しておくことが重要です。
退職後の転職を有利に進めるためのポイント
退職してから転職活動をすることがすべて悪いわけではありません。
むしろ、じっくりと次のキャリアを考えたり、スキルアップの時間を確保したりするメリットもあります。
しかし、成功させるためには事前の準備が欠かせません。
- 貯金を確保する:最低でも6ヶ月分の生活費を用意し、焦らず転職活動ができるようにする。
- 転職活動の計画を立てる:退職前に求人の市場調査をし、どの企業に応募するかを決めておく。
- ブランク期間を有効活用する:スキルアップのための資格取得や、業界のトレンドを学ぶ時間に充てる。
- 転職エージェントを活用する:効率的に求人情報を得ることで、短期間での転職成功率を上げる。
【総括】退職後の転職活動は必ずしも不利にはならないが注意が必要
退職してから転職活動を始めることは、必ずしも不利とは言えません。
しかし、転職市場では「働きながら転職活動をする方が有利」とされる傾向があります。
ブランクが長引くと採用担当者の印象が悪くなったり、経済的な不安から希望条件を妥協してしまうこともあるため、慎重に進めることが大切です。
もし退職後に転職を進める場合は、計画的に行動し、無職期間が長くならないように準備を整えておくことが成功のカギとなります。
転職活動期間を働きながら成功させるコツ
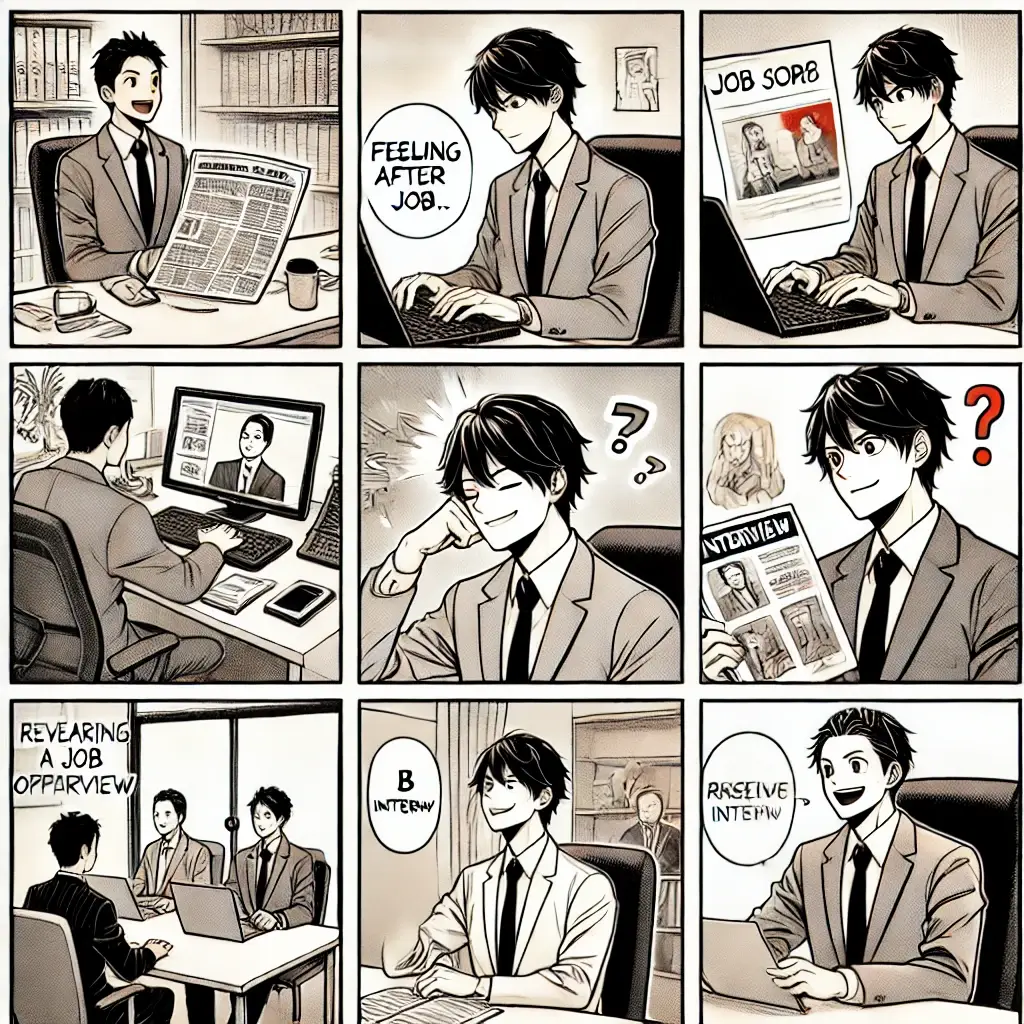
転職を成功させるためには、計画的な準備が必要です。
しかし、現在の仕事を続けながら転職活動を進めるのは、時間的にも精神的にも負担が大きく、思うように進まないこともあります。
なので、「仕事を辞めてから転職したほうが効率的なのでは?」と考えるかもしれません。
しかし、転職市場では 「働きながら転職活動をする方が有利」 と言われることが多く、実際に採用担当者の印象も良くなりやすいです。
では、忙しい中でもスムーズに転職を進め、理想の企業へ転職するにはどうすればよいのでしょうか?
ここでは、働きながら転職を成功させるための具体的なコツを見て行きます。
転職活動のスケジュールを立てる
まず、転職活動を始める前に、無理なく進められるスケジュールを立てましょう。
仕事をしながら転職活動をする場合、時間の使い方が鍵になります。
- 転職の目的・希望条件を整理する(1〜2週間)
- どんな仕事をしたいのか、どの業界・職種が自分に合っているのかを明確にする。
- 希望する給与や勤務地、福利厚生など、譲れない条件をリストアップする。
- 求人情報を集める(2〜3週間)
- 転職サイトや転職エージェントを活用し、自分に合った求人をピックアップする。
- 企業研究を進め、応募書類を準備する。
- 応募・面接を進める(1〜2ヶ月)
- 企業ごとの応募スケジュールを確認し、計画的にエントリーする。
- 面接の対策をしっかり行い、選考を突破する。
- 内定・退職準備(1ヶ月)
- 内定をもらったら、現職の退職手続きを進める。
- 円満退職を心がけ、引き継ぎをスムーズに進める。
このように、働きながら転職を進める場合は、1つ1つのステップを計画的に進めることが重要です。
2. 求人情報の収集は効率的に
仕事をしながら求人情報を探すのは意外と時間がかかります。効率よく情報を集めるために、以下の方法を活用しましょう。
転職サイトを活用する
転職サイトには、希望条件を登録しておけば、自動でおすすめの求人を紹介してくれる機能があります。
興味のある企業の新着情報を見逃さないよう、通知設定を活用するのも有効です。
転職エージェントを利用する
転職エージェントに登録すると、担当者が自分の希望に合った求人を紹介してくれます。
また、履歴書や職務経歴書の添削、面接対策のサポートも受けられるため、忙しい人には特におすすめです。
個人的にオススメなのが、機械設計に特化したエージェントを選ぶことです。
元設計者がエージェントをしている事が多く、今現在のエンジニアとしての悩みも聞いてくれるし、設計業界や案件を熟知しているので、結果的にかなりの時短になると思いますよ。
企業の口コミや評判をチェックする
求人情報だけでは分からない、企業の実際の雰囲気や労働環境を知るためには、口コミサイトを活用しましょう。
社風や残業の実態、職場の人間関係など、リアルな情報を参考にすることで、ミスマッチを防ぐことができます。
3. 応募書類は事前に準備しておく
転職活動をスムーズに進めるためには、履歴書や職務経歴書の準備を早めに済ませておくことが大切です。
仕事をしながらだと、応募書類を作成する時間を確保するのが難しくなるため、あらかじめベースとなる書類を作成しておき、応募する企業ごとに微調整する方法 が効果的です。
- 履歴書はフォーマットを統一し、使い回せるようにする
- 職務経歴書は、応募企業ごとに内容を最適化する(例えば、強調するスキルや経験を変える)
- 転職エージェントを活用し、書類の添削を受ける
こうすることで、応募のたびに1から書類を作る手間を省き、効率よく転職活動を進めることができます。
4. 面接の日程調整を工夫する
働きながら面接を受ける場合、スケジュール調整が難しくなります。
面接日程の調整がうまくいかないと、せっかくのチャンスを逃してしまうこともあるため、以下のような方法で対応しましょう。
有給休暇や半休を活用する
有給休暇を活用して、まとめて複数の企業の面接を受けると効率的です。
また、半休制度がある場合は、午前中や午後の時間を活用して面接に行くのも良いでしょう。
リモート面接を希望する
最近では、オンラインでの面接を実施する企業も増えています。
特に一次面接はリモートで行う企業が多いため、出社前や仕事終わりに対応できるか相談してみるのもおすすめです。
今現在の状況は分かりませんが、私が直近の40代で転職活動していた時はコロナの影響もあって、最終面接まで全てWEB面談だったので、無理なく転職活動できました。
リモートが可能であれば、地方の有名メーカーとの面談も可能なので、利用できる場合は積極的に打診してみましょう。
昼休みやフレックスタイムを利用する
昼休みの時間を活用したり、フレックスタイム制を利用して勤務時間を調整することで、面接の時間を確保しやすくなります。
5. 退職のタイミングを慎重に見極める
内定をもらったからといって、すぐに退職を申し出るのは避けましょう。
入社日が確定するまでは、現在の職場に留まることが大切です。
- 入社日が正式に決まっているか(内定通知書に記載されているか)
- 現職の退職手続きに必要な期間(引き継ぎや有給消化の期間を考慮)
- 転職先の労働条件や待遇に納得しているか
焦って退職すると、万が一転職先が決まらなかった場合にリスクが高くなるため、確実に次の職場が決まるまでは慎重に行動しましょう。
【総括】計画を立て、利用できるものは全て利用しましょう
仕事を続けながら転職活動をするのは大変ですが、スケジュールを立て、効率的に進めることで成功率を高めることができます。
特に、
- 求人情報の収集
- 応募書類の準備
- 面接の日程調整
- 退職のタイミング
を意識することで、スムーズに転職を進めることが可能です。
「今の仕事が忙しくて転職活動が進められない」と感じる人も、計画的に行動すれば、働きながらでも転職を成功させることは十分可能です。
焦らず、着実に次のキャリアへと進んでいきましょう。
辞めてから転職を成功させるメリットとは?
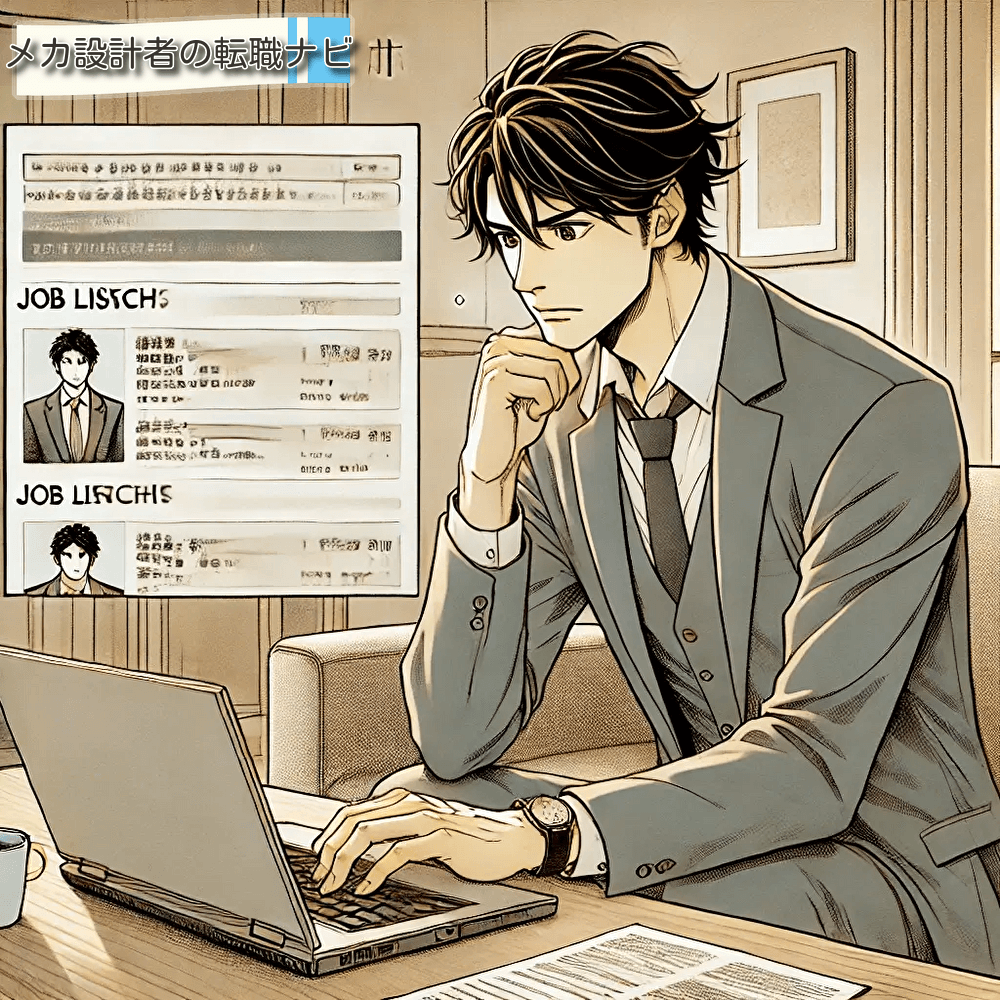
転職活動は、働きながら進めるのが一般的とされていますが、仕事を辞めてから転職活動に専念する選択肢もあります。
退職してからの転職はリスクが高い
と言われることが多いものの、状況によってはメリットも大きく、成功しやすいケースもあります。
ここでは、仕事を辞めてから転職活動を行うことで得られるメリットを詳しく見て行きます。
転職活動に集中できる
最も大きなメリットは、転職活動に専念できることです。
働きながら転職活動をする場合、仕事の合間を縫って求人を探し、履歴書を作成し、面接のスケジュールを調整しなければなりません。
業務が忙しいと転職活動に時間を割けず、結果として準備不足のまま面接に臨んでしまい、選考で不利になることもあります。
一方で、退職後であれば、時間的な余裕ができるため、企業研究をじっくり行い、職務経歴書のブラッシュアップや面接対策に十分な時間を確保できます。
また、平日の日中に面接を受けられるため、企業側の都合に合わせやすく、選考がスムーズに進むという利点もあります。
- 企業研究や自己分析を深める時間が取れる
- 面接対策を十分に行える
- 応募企業の都合に合わせやすく、選考が進みやすい
ストレスを減らし、冷静な判断ができる
働きながら転職活動をする場合、現在の仕事のストレスと転職活動のプレッシャーが重なり、精神的に疲弊しやすくなります。
特に、今の職場で人間関係に悩んでいたり、長時間労働で疲れていたりすると、冷静な判断が難しくなり、
と焦ってしまうことも…。
一方、退職してから転職活動をする場合、仕事のストレスから解放され、落ち着いて自分のキャリアと向き合うことができます。
時間をかけて希望する企業を選び、納得のいく転職先を見つけることが可能です。
- 転職活動のストレスを減らせる
- 冷静に企業を選ぶことができる
- 焦らず、自分に合った転職先を見極められる
スキルアップや資格取得の時間を確保できる
転職活動の期間を、単なる「転職先探しの時間」ではなく、自分の市場価値を高める時間として活用できるのも大きなメリットです。
特に、次の転職先で求められるスキルが明確な場合、資格取得や勉強に時間を使うことで、希望する企業への内定率を高めることができます。
例えば、IT業界への転職を目指す場合はプログラミングの勉強を進めたり、事務職ならMOS(マイクロソフトオフィススペシャリスト)や簿記の資格を取得したりすることで、転職活動を有利に進められます。
また、語学力が必要な職種では、TOEICのスコアを上げるための学習をするのも有効です。
- 転職先に求められるスキルを身につけられる
- 資格を取得して市場価値を高められる
- キャリアアップのための準備ができる
キャリアチェンジの可能性が広がる
働きながらの転職活動では、どうしても 「今までの経験を活かせる仕事」 に応募しがちです。
しかし、退職後は時間的な余裕があるため、業界や職種を大きく変えるキャリアチェンジを検討することも可能になります。
例えば、営業職からWebマーケティング職への転職を考えている場合、転職活動の合間にオンラインスクールでスキルを習得し、ポートフォリオを作成することで未経験からの転職がしやすくなります。
また、エンジニアやデザイナーなど、専門的なスキルが必要な職種でも、学習期間を設けることでチャンスを広げることができます。
- 未経験の業界・職種へ挑戦しやすくなる
- スキルを身につけながら転職活動ができる
- やりたい仕事に向けた準備期間を確保できる
【総括】退職後の転職活動は時間
退職してから転職活動をするのはリスクもありますが、
「転職活動に集中できる」
「ストレスなく冷静に判断できる」
「スキルアップの時間が確保できる」
「キャリアチェンジしやすい」
など、多くのメリットもあります。
特に、現職が忙しすぎて転職活動の時間が取れない人や、転職に向けてスキルアップが必要な人にとっては、退職後にじっくりと活動するほうが成功しやすいケースもあります。
ただし、生活費や転職活動期間の計画をしっかり立てておかないと、焦りから妥協して転職先を決めてしまうリスクもあるため、慎重に検討することが大切です。
「退職後に転職活動をするべきか迷っている」という場合は、自分の状況や優先順位を考えながら、どちらの方法が適しているかを判断しましょう。
辞めてから転職する人の割合はどれくらい?
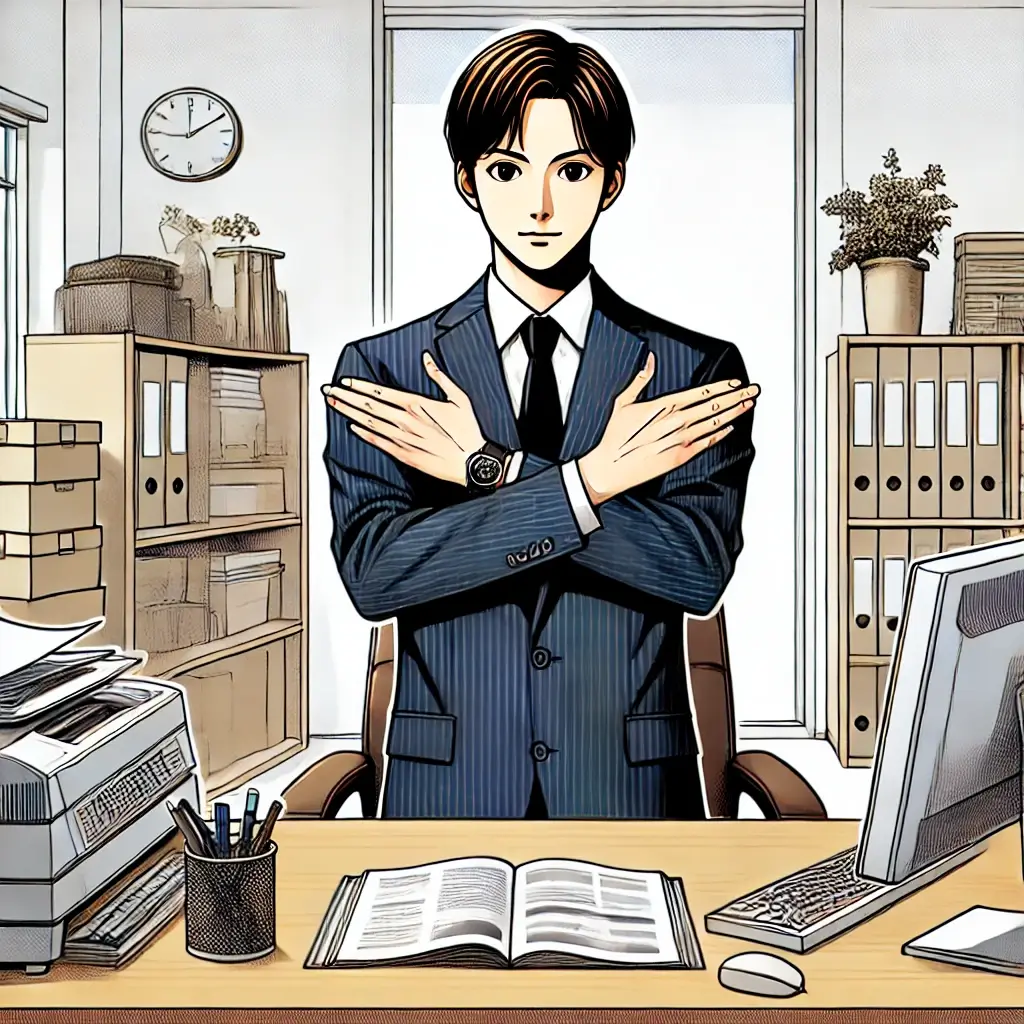
いきなり結論から入りますが、
とされています。
つまり、転職を考える人の約4人に1人が、仕事を辞めた後に転職活動をしているということになります。
ただし、業界や職種、個人の状況によってもこの割合は変動し、年齢や経済状況などが影響することが多いです。
転職サイトや転職エージェントの調査によると、
という結果が出ています。
特に、20代・30代の若手層は在職中に転職活動を行うケースが多いのに対し、40代以降の転職者では、いったん退職してから転職活動に専念する人の割合がやや増える傾向があります。
また、総務省統計局の「労働力調査」によると、2023年の転職者数は約325万人で、就業者全体に占める転職者の割合(転職者比率)は約4.8%とされています。
このデータからも、一定数の人が転職を選択していることがわかります。
さらに、厚生労働省の雇用動向調査では、
との結果が出ています。
特に、精神的な負担が大きい職場環境で働いている人や、キャリアチェンジを考えている人にとっては、一度仕事を辞めてから次の職を探すことが選択肢になりやすいようです。
【総括】退職後の転職は事前準備が大事
統計データを見ても、転職を考える人の中で退職してから活動する割合は決して少なくありません。
特に40代以上や、現職に強いストレスを抱えている人、キャリアチェンジを目指す人の中には、退職してから転職活動を行うケースが多い傾向があります。
ただし、退職後の転職活動には経済的な負担や転職活動期間の長期化といったリスクも伴います。
そのため、退職後の転職を選択する場合は、事前に生活費の確保や転職市場のリサーチを行い、スムーズに次の職場を見つけられるように準備を進めることが大切です。
次の仕事決まってないけど辞めるリスク【40代編】
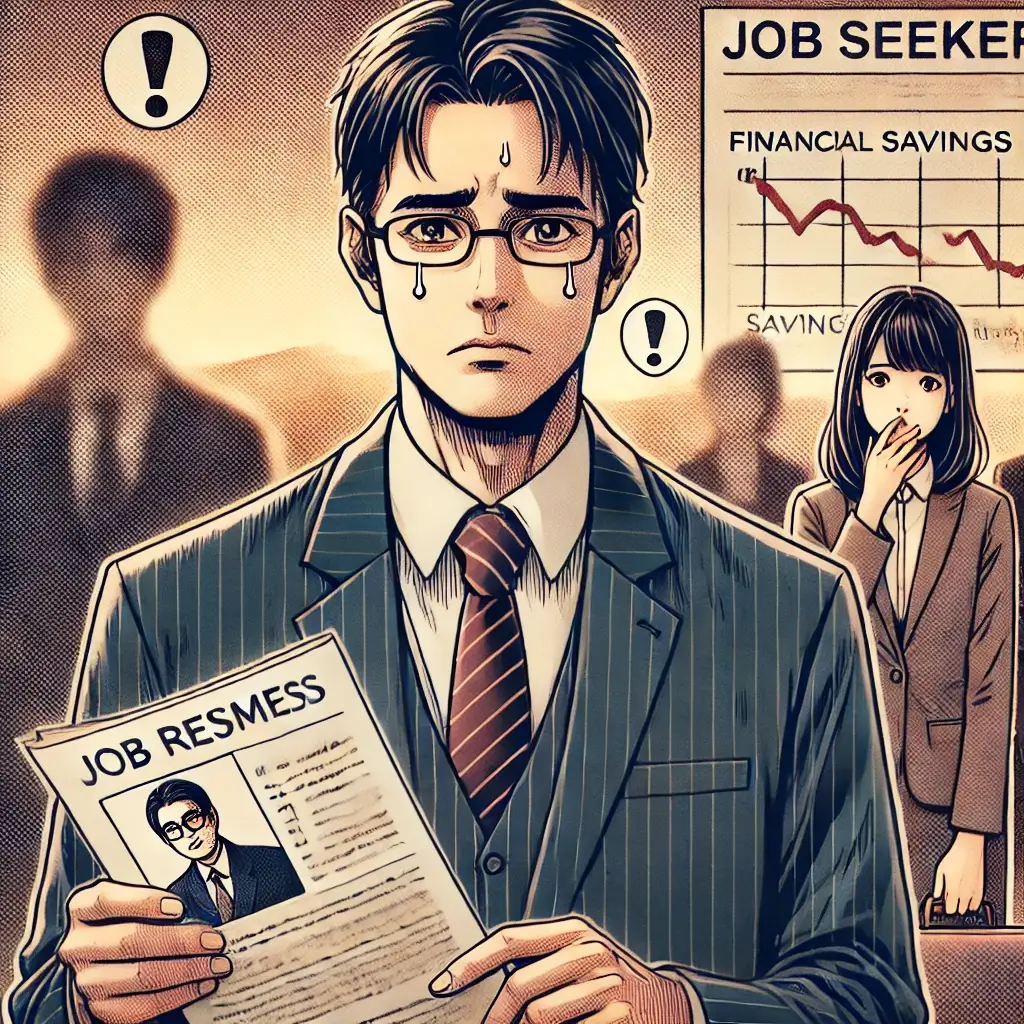
40代で次の仕事が決まっていない状態で退職することには、大きなリスクがあります。
転職活動の長期化、収入の途絶、再就職の難易度の上昇など、20代・30代と比べて不利な状況に陥りやすいため、慎重な判断が求められます。
特に、家族を養っている人やローンを抱えている人は、経済的な余裕がないまま退職すると大きな負担になる可能性が高いため、十分な準備が必要です。
40代が転職活動で直面しやすいリスク
40代で仕事を辞めてから転職を考える場合、次のようなリスクが生じやすくなります。
転職活動が長期化しやすい
40代の転職市場は、20代・30代と比べると求人数が少なく、即戦力やマネジメント経験が求められるケースが多いため、自分に合った企業を見つけるまでに時間がかかることが多いです。
厚生労働省の調査では、40代の転職活動期間は平均6ヶ月以上かかることが多く、場合によっては1年以上かかることも珍しくありません。
収入が途絶えることで生活が厳しくなる
仕事を辞めると当然ながら収入がゼロになります。
貯蓄が十分でないと、家賃やローン、生活費の支払いが厳しくなり、精神的な焦りから妥協した転職先を選ばざるを得なくなる可能性があります。
特に、40代は子どもの教育費や住宅ローンの支払いが重なる時期でもあり、貯金なしで退職すると生活が一気に苦しくなるリスクが高まります。
再就職の難易度が上がる
40代は、企業側が求めるスキルや経験がより具体的になります。
そのため、これまでのキャリアと関連性の低い職種への転職は難しくなる傾向があります。
また、企業は40代の採用に慎重になることが多く、
「給与が高くなりやすい」
「組織に馴染みにくい」
といった懸念を抱かれることも少なくありません。
そのため、求人の選択肢が狭まり、納得できる仕事が見つかるまでに時間がかかるケースが多いのです。
精神的なプレッシャーが大きい
40代になると「早く仕事を決めないといけない」というプレッシャーが強くなりがちです。
特に、家族を養っている場合は、周囲からのプレッシャーや将来への不安が増し、精神的なストレスが大きくなることが考えられます。
焦って転職先を決めてしまうと、ブラック企業に入社してしまったり、望まない職種に就いてしまうリスクもあります。
40代が転職前に準備すべきこと
40代で仕事を辞める前に、次のような準備をすることでリスクを軽減できます。
- 生活費の確保(最低でも6ヶ月分の貯蓄を準備)
→ 転職活動の長期化を見越して、余裕を持った資金計画を立てる - スキルや経験の棚卸しをして、転職市場のニーズを把握する
→ これまでのキャリアを整理し、どの業界・職種で求められるか分析する - 転職エージェントに相談して、転職の可能性を確認する
→ 事前に転職活動の難易度を知り、辞める前に転職の道筋を立てる - 副業やフリーランスの選択肢も考慮する
→ すぐに転職先が決まらない場合でも収入を確保できる手段を用意する
【総括】リスクを最小限にするために準備が必要
40代で仕事を辞めてから転職活動をするのは、リスクが非常に大きい選択となります。
特に、
- 転職活動の長期化
- 収入の途絶
- 再就職の難しさ
といった課題に直面しやすく、準備なしに退職することは危険です。
しかし、十分な貯蓄やスキルの整理、転職市場のリサーチを行えば、リスクを最小限に抑えることが可能です。
40代の転職は慎重な準備が必要ですが、適切な対策を取ることで、より良いキャリアを築くこともできます。
退職してから転職した場合の失業保険について
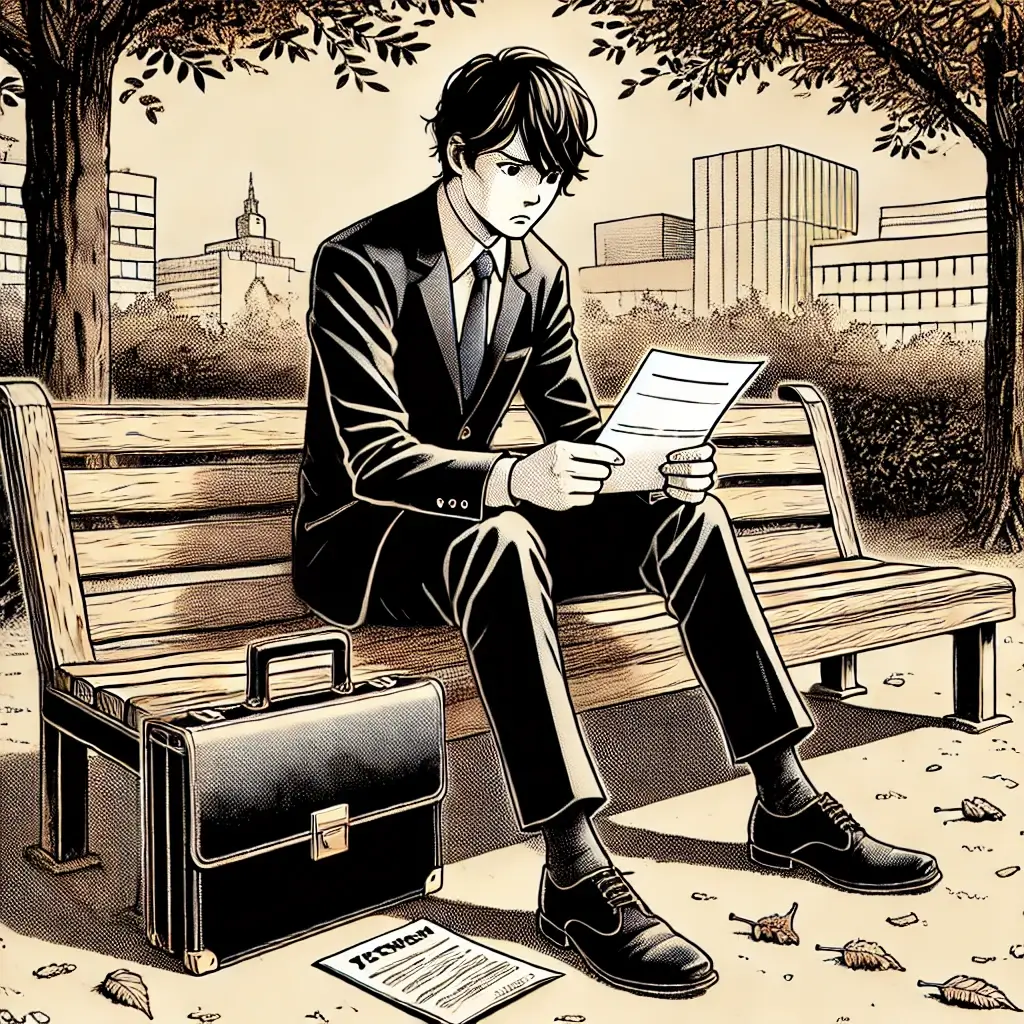
失業保険(雇用保険)の基本ルール
会社を退職すると、一定の条件を満たせば「失業保険(正式には雇用保険の基本手当)」を受給できます。
この失業保険は、次の仕事が決まるまでの生活費の一部を補助するための制度で、求職活動を行う人が対象となります。
ただし、受給には条件があり、申請のタイミングや給付開始までの待機期間もあるため、あらかじめ仕組みを理解しておくことが重要です。
失業保険を受給するための条件
失業保険を受け取るには、以下の条件を満たす必要があります。
- 雇用保険に加入していた期間が一定以上あること
→ 退職前の2年間に通算12ヶ月以上、雇用保険に加入していたこと
(倒産・解雇など会社都合退職の場合は、1年間で6ヶ月以上でOK) - ハローワークで求職活動を行い、就職の意思があること
→ 失業保険は「働く意思がある人」向けの制度のため、求職活動をしていないと受給できない - 自己都合退職か会社都合退職かによって給付条件が変わる
→ 会社都合退職(解雇・倒産など)の場合、受給開始が早く、給付期間も長くなる
→ 自己都合退職(転職のために自ら辞めた場合)は、給付までに3ヶ月の給付制限期間がある
自己都合退職と会社都合退職の違い
失業保険の受給条件は、退職理由によって大きく変わります。
| 項目 | 会社都合退職 | 自己都合退職 |
|---|---|---|
| 給付開始時期 | 7日間の待機後すぐ | 3ヶ月の給付制限あり |
| 給付期間 | 長め(90日〜330日) | 短め(90日〜150日) |
| 条件 | 1年のうち6ヶ月以上勤務 | 2年のうち12ヶ月以上勤務 |
会社都合退職の方が圧倒的に有利なため、退職前に「自分の退職理由が会社都合として認められるか」を確認することが重要です。
例えば、以下のようなケースは会社都合退職と認められる可能性があります。
- 会社の業績悪化によるリストラ
- 会社が倒産した場合
- 長時間労働やハラスメントが原因で退職した場合(証拠が必要)
- 契約期間満了で更新されなかった場合
失業保険の受給手続き
失業保険を受け取るには、退職後にハローワークで手続きをする必要があります。
主な流れは以下のとおりです。
- 離職票を受け取る(退職後、会社から発行される)
- ハローワークで求職申込をする(持ち物:離職票、マイナンバーカード、通帳など)
- 雇用保険説明会に参加する(約1週間後)
- 7日間の待機期間を過ごす(この間は働けない)
- 自己都合退職の場合は3ヶ月の給付制限を経て受給開始
- 求職活動を継続し、認定日ごとにハローワークで報告する
※自己都合退職の場合は3ヶ月間の給付制限があるため、この間は無収入となる点に注意が必要です。
もらえる失業保険の金額
失業保険の給付額は、退職前の給与によって決まります。
基本的な計算式は以下のとおりです。
基本手当日額の計算
退職前6ヶ月の給与の合計 ÷ 180日 × 給付率(50〜80%)
例えば、退職前の月収が30万円だった場合:
- 30万円 × 6ヶ月 = 180万円
- 180万円 ÷ 180日 = 1万円(1日あたりの賃金)
- 給付率が60%の場合 → 1日6,000円の給付
※年齢や前職の給与によって給付率が異なるため、詳細はハローワークで確認が必要です。
失業保険を有効活用するためのポイント
- 退職前に雇用保険の加入期間を確認する
→ 12ヶ月以上勤務していないと受給資格がないため、在籍期間をチェック - なるべく会社都合退職として認められるようにする
→ ハラスメントや過労が原因の場合、証拠を集めて会社都合扱いを申請できる - 給付制限期間を考慮して、貯金を確保する
→ 自己都合退職の場合、3ヶ月間無収入になるため、その間の生活費を準備 - 失業保険受給中も積極的に転職活動を行う
→ 失業保険は「求職活動をしている人向け」の制度のため、ハローワークでの報告が必須
【総括】早めに転職先を見つけるのが基本
退職してから転職活動をする場合、失業保険を活用することで一定期間の生活費を補うことが可能です。
しかし、自己都合退職の場合は3ヶ月の給付制限があるため、無収入期間を考慮した資金計画が必要です。
また、会社都合退職であれば、受給開始が早く給付期間も長くなるため、自分の退職理由を見直し、会社都合として認められるか確認することも重要です。
失業保険はあくまで「求職中の生活を支えるための制度」であり、早めに転職先を見つけることが最善の選択となるでしょう。