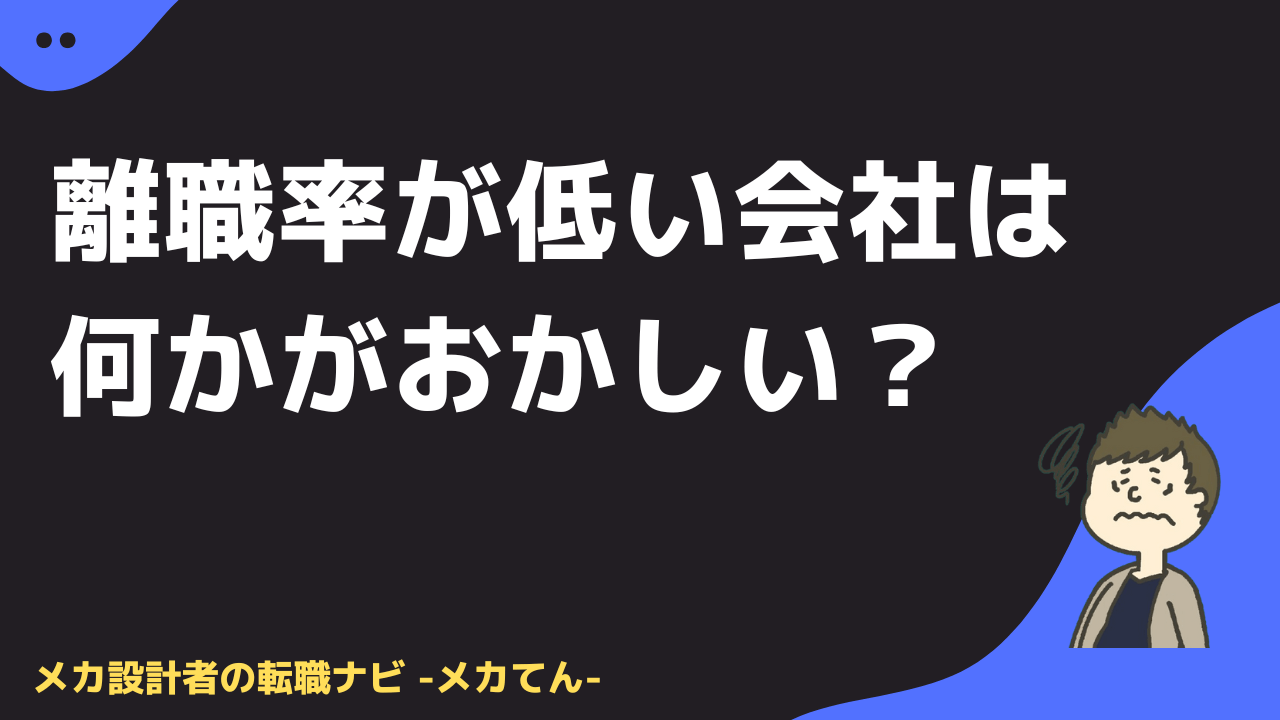結論から言うと、「離職率の高さ=悪」でもなければ、「離職率の低さ=ホワイト企業」とは限りません。
これから転職を考えている人にとって、「離職率」という数字は会社の良し悪しを見極める重要な指標のひとつ。
でも、数字だけを見て「辞める人が多いからブラックだ」と判断するのは早計ですし、逆に「誰も辞めていない=居心地がいい会社」とも限らないのが現実です。
この記事では、離職率が高い会社・低い会社、それぞれの裏側にある「本当の理由」や「注意すべきポイント」について詳しく見て行きます。
あなたにとって本当に合った職場を見つけるためのヒントになるはずです。
離職率が低い会社は何かがおかしい?
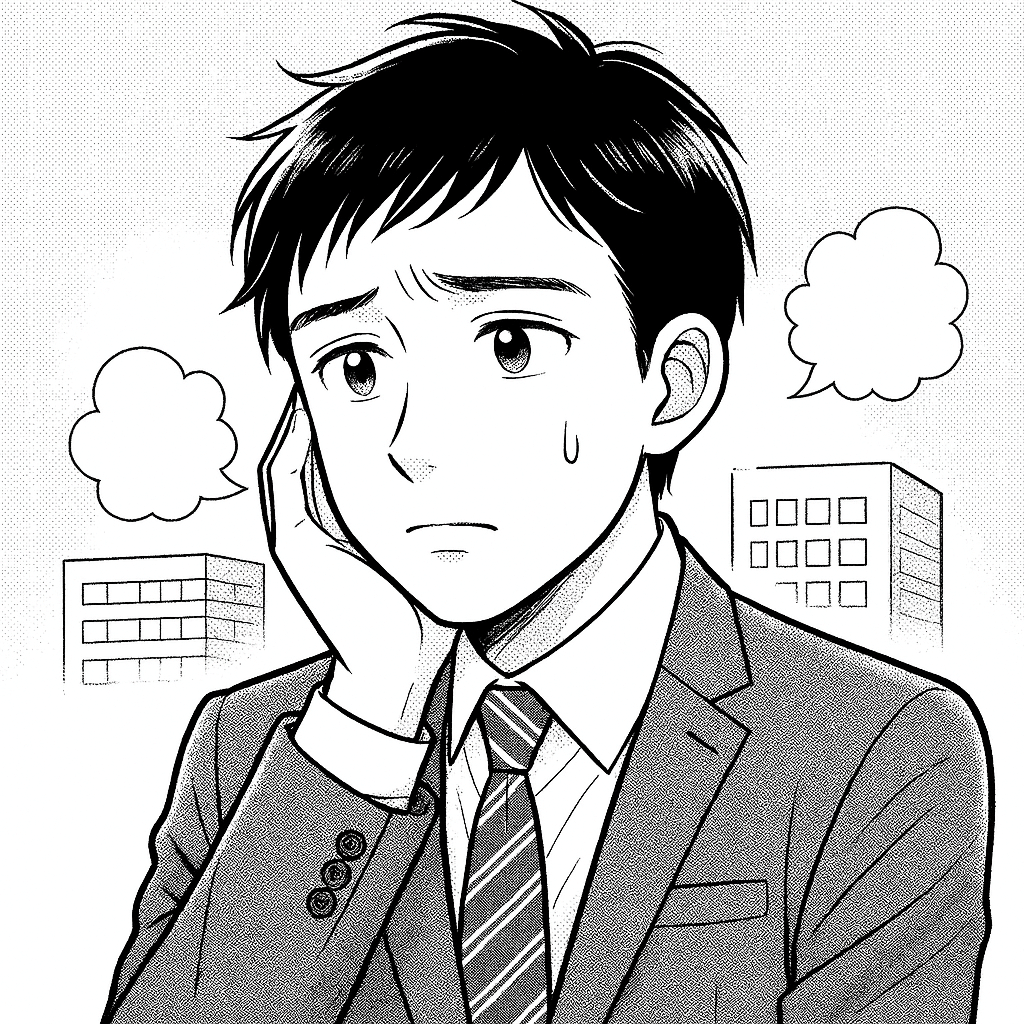
一見「離職率が低い=ホワイト企業」と思われがちですが、実はそうとは限りません。
数字の裏には、必ず理由や背景があります。
転職活動中に「この会社、離職率がすごく低いから安心だな」と思ったとしても、もう一歩踏み込んで考える視点が必要です。
社員が“辞められない”雰囲気に包まれている場合もある
離職率が極端に低い会社では、「辞めにくい空気」が存在していることがあります。
たとえば、
- 上司や同僚が辞職をネガティブに捉える文化がある
- 退職を伝えた人が悪者扱いされた過去がある
- 辞めることで評価や人間関係が壊れると恐れている
こうした環境では、たとえ社員が不満やストレスを抱えていても、表には出さずに耐える傾向が強くなります。
表面上は穏やかでも、内側ではモチベーションが下がり続けている…そんなケースも珍しくありません。
「変化を嫌う文化」が根付いている可能性
長く同じメンバーが働き続けている組織には、
といった空気が流れていることがあります。
新しい挑戦を好む人や、自分の成長を重視したいタイプにとって、こうした保守的な組織風土は大きなストレスになります。
実際に、若手や中堅社員が
と感じている場合、転職を考えていても口に出せないまま時間だけが過ぎていくことも。
「評価があいまい」でも誰も文句を言わない組織
社員が辞めない理由が「安定しているから」というケースもあります。
もちろん安定は大事ですが、裏を返せば
「頑張っても評価されない」
「やる気がなくてもクビにならない」
という状況が続いている可能性も。
たとえば、10年間同じ仕事をしていても昇給や昇格が曖昧なままだと、やりがいを失っていく人が出てきます。
それでも生活ができるから…と残り続ける社員が多い場合、組織は徐々に活力を失っていきます。
つまり、「辞めない=満足している」とは限らないのです。
【総括】離職率の“低さ”だけで判断するのは危険
離職率の低さは、一見すると安定性や働きやすさの指標に思えます。
しかし、その数字の裏側には、
- 辞めにくい雰囲気
- 変化を拒む文化
- 評価制度の曖昧さ
など、組織の課題が隠れていることもあるのです。
大切なのは、「なぜ辞める人が少ないのか?」という理由を見極めること。
会社説明会や面接で質問してみたり、口コミサイトをチェックしたりして、実態を掘り下げていきましょう。
「辞めない人が多い」ことが、必ずしも「居心地が良い会社」という意味ではない――この視点を持つことで、より納得のいく転職先選びができるはずです。
いわゆる「ぶら下がり社員」は何が悪い?
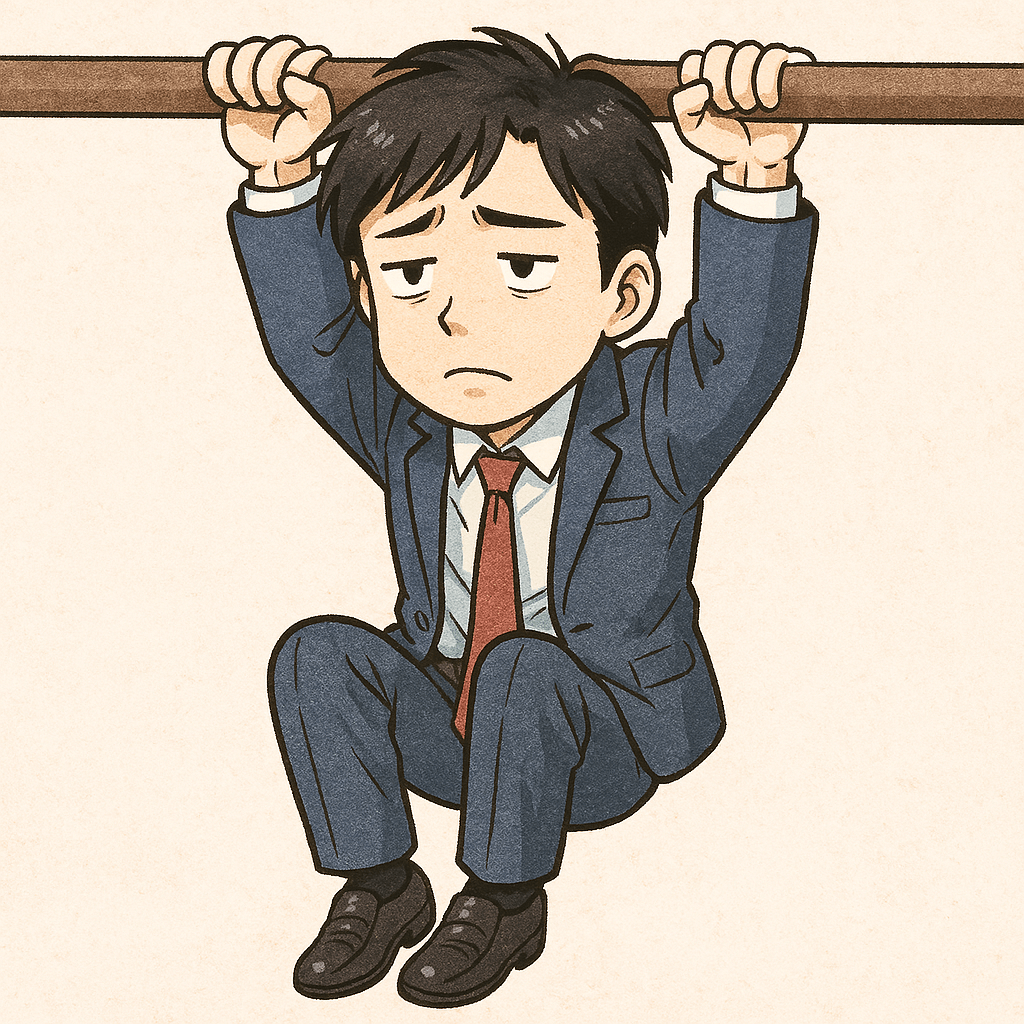
「ぶら下がり社員」とは、自ら積極的に働くことはせず、与えられた最低限の業務だけをこなし、会社の中でなんとなく居座っている社員のことを指します。
こうした存在が職場に増えると、組織全体の生産性や雰囲気に大きな悪影響を与える恐れがあります。
周囲のモチベーションを下げてしまう
ぶら下がり社員の最大の問題点は、周囲のやる気を奪ってしまうことです。
たとえば、真面目に努力している社員が、評価されることもなく、何年も同じポジションに留まっている一方で、やる気のないぶら下がり社員が同じ待遇を受けていたら…どう感じるでしょうか?
と考えてしまうのは、ごく自然な流れです。
結果として、組織全体のモチベーションが落ちていきます。
若手の成長のチャンスを奪う存在にもなる
ぶら下がり社員が職場に長く居座ることで、本来であれば若手や中堅社員にチャンスが回るはずのポジションが塞がれてしまうケースがあります。
特に、年功序列の色が濃い職場では、
ということが起きやすく、若手がキャリアを描きにくくなります。
そうした会社では、
と不満を感じた人から順に、会社を離れていくことになります。
「働かなくても居られる」文化が根づいてしまう
ぶら下がり社員の存在を許容し続けると、それは次第に社風や文化として定着していきます。
「結局、頑張らなくてもクビにならない」
「適当にやっててもなんとかなる」
という空気が広がれば、真面目にやってきた人たちも少しずつ手を抜き始めるでしょう。
最終的には、会社全体が「停滞」することになります。
企業にとって最も危険なのは、成長を止めること。
ぶら下がり社員を放置するというのは、まさにその入口になり得るのです。
【総括】ぶら下がり社員は“悪”ではないが、“課題”である
もちろん、ぶら下がり社員のすべてが「悪意ある怠け者」というわけではありません。
中には、会社の評価制度に失望し、燃え尽きてしまった人もいるでしょうし、ライフスタイルの変化から無理をしない働き方を選んでいるだけの人もいるでしょう。
ただし、組織の中でそういったスタンスの人が増えると、周囲への影響は大きくなります。
個人の生き方としては問題がなくても、
「周囲にどんな影響を与えるか」
「組織としてどう対処すべきか」
という視点で捉える必要があります。
転職活動中であれば、職場の雰囲気や評価制度、昇進のスピード感などに注目することで、
を見極めるヒントになります。
離職率が高い会社は何がいけない?退職者が多い原因とは?

離職率が高い会社には、組織の中に「人が定着しにくい何かしらの理由」があるケースがほとんどです。
単なる偶然ではなく、職場環境やマネジメント、評価制度など、構造的な課題が根底にあると考えるべきです。
人が辞める職場には、共通する“働きづらさ”がある
離職率が高い会社では、必ずといっていいほど「働きづらさ」を感じる要素が存在します。
例えば、
- 終わらない長時間労働
- 曖昧な指示と責任の押しつけ合い
- 上司のパワハラ、無関心、過干渉
- 評価が不透明で昇給・昇格の道筋が見えない
こうした職場では、どんなにやる気のある社員でも疲弊し、「ここにいても成長できない」と感じてしまいます。
つまり、「辞めた人」よりも「辞めずにいる人」の方が、我慢強いか適応力が高いだけという場合もあり、会社側の問題が放置されたままになっていることも珍しくありません。
社員が育たず、悪循環が続く
離職率が高いと、常に新しい人材が入っては辞めていくことになります。
これが繰り返されると、会社にノウハウや経験が蓄積されず、人が育たない組織になってしまいます。
そうなるとどうなるか?
- 教える人がいないから新人が育たない
- 人手が足りず、業務が属人化する
- ベテランに負担が集中し、さらに退職者が出る
このようにして、負のスパイラルに陥っていくのです。
「人が辞めるから育たない」
「育たないから辞める」
の繰り返しは、企業にとって非常に大きな損失です。
人材こそが会社の資産であることを考えると、この状況を放置することは、将来的な競争力の低下にもつながります。
離職率が高い企業ほど「人が辞めても仕方ない」という空気に慣れてしまう
もう一つ見逃せないのが、「辞めるのが当たり前」という空気が職場に蔓延することです。
このような諦めや冷めた感情が当たり前になると、チームとしての一体感や協力意識はどんどん失われていきます。
本来、職場は「安心して働ける場所」であるべきです。
ところが、離職が常態化している会社では、その信頼関係が築けません。
人が辞めることに対して何も対策をしない会社では、社員が未来を描けなくなるのです。
【総括】人が辞める背景を「個人の問題」として片づける会社は要注意
退職者が多い会社に共通するのは、
です。
そんな言葉で片づけてしまう会社は、構造的な問題に気づけないまま、また新たな退職者を生み続けてしまいます。
もし、転職活動中に「この会社、やたらと退職者が多いな」と感じたら、その理由をしっかり見極めましょう。
口コミや面接時の空気感、社員の平均在籍年数などをチェックするのがおすすめです。
離職率が高いという基準は何パーセントから?
一般的に、年間の離職率が15%を超えてくると「やや高い」、20%を超えると「かなり高い」とされる傾向にあります。
ただし、これは業界や職種によって大きく異なるため、数字だけで「良い・悪い」を判断するのは危険です。
業界ごとに違う「当たり前の離職率」
たとえば以下のように、業種によって「普通」とされる離職率の水準は異なります。
- 介護・飲食・小売業などのサービス業:30〜50%も珍しくない
- IT業界やスタートアップ企業:20〜30%前後
- 製造業やインフラ系、大企業:5〜10%前後が一般的
つまり、10%の離職率でも“高い”とされる業界もあれば、20%でも“安定している”と見なされる業界もあるということです。
自分が目指す業界や会社の平均値を把握した上で、「高い」と言えるかどうかを判断することが大切です。
離職率の出し方を知ると見え方が変わる
離職率は基本的に、以下の式で算出されます。
たとえば、期首に100人いた会社で1年間に20人が辞めた場合、離職率は「20%」になります。
しかしここで注意が必要なのは、「社員数が少ない会社ほど、少人数の退職で離職率が大きく動く」という点です。
- 5人中1人が辞めただけで離職率は20%
- 10人中2人で同じく20%
このように、小規模な企業では離職率の見た目以上に現場への影響が大きくなることもありますし、逆に「数字ほど問題がないケース」も存在します。
つまり、単なる数字の比較ではなく、社員数の規模や職場の実態も踏まえて考える必要があるのです。
離職率だけで会社の良し悪しは判断できない
離職率の数字はあくまでも「一つの参考情報」に過ぎません。
重要なのは、
- なぜ辞めているのか
- 辞めた後の声(口コミや評判)
- 辞めた人の立場やタイミング(中堅?新卒?)
といった“中身”です。
たとえば、
- 「若手が成長して次のステップに進むために辞めている」
- 「評価制度が変わって一時的に辞める人が増えた」
というケースであれば、一概に悪いとは言えません。
逆に、
- 「ハラスメントで辞めた」
- 「上司のえこひいきに耐えられなかった」
といった背景があれば、数字が低くても問題は根深い可能性があります。
【総括】「何パーセントなら悪い」ではなく、「なぜ辞めたのか」が重要
離職率が高いかどうかの基準は、単純に数字だけで判断してはいけません。
重要なのは、その会社の離職理由や社員の声、業界全体の傾向を把握することです。
もし転職先を検討していて、「離職率20%」と聞いた場合は、「どうしてそんなに人が辞めているのか?」を確認しましょう。
口コミや面接時の質問で見えてくることも多くあります。
離職率の数字は、あくまで企業を見極めるための「ヒントのひとつ」として活用するのが正しいスタンスです。
離職率が高い会社が辞めたいと言われる5つの理由
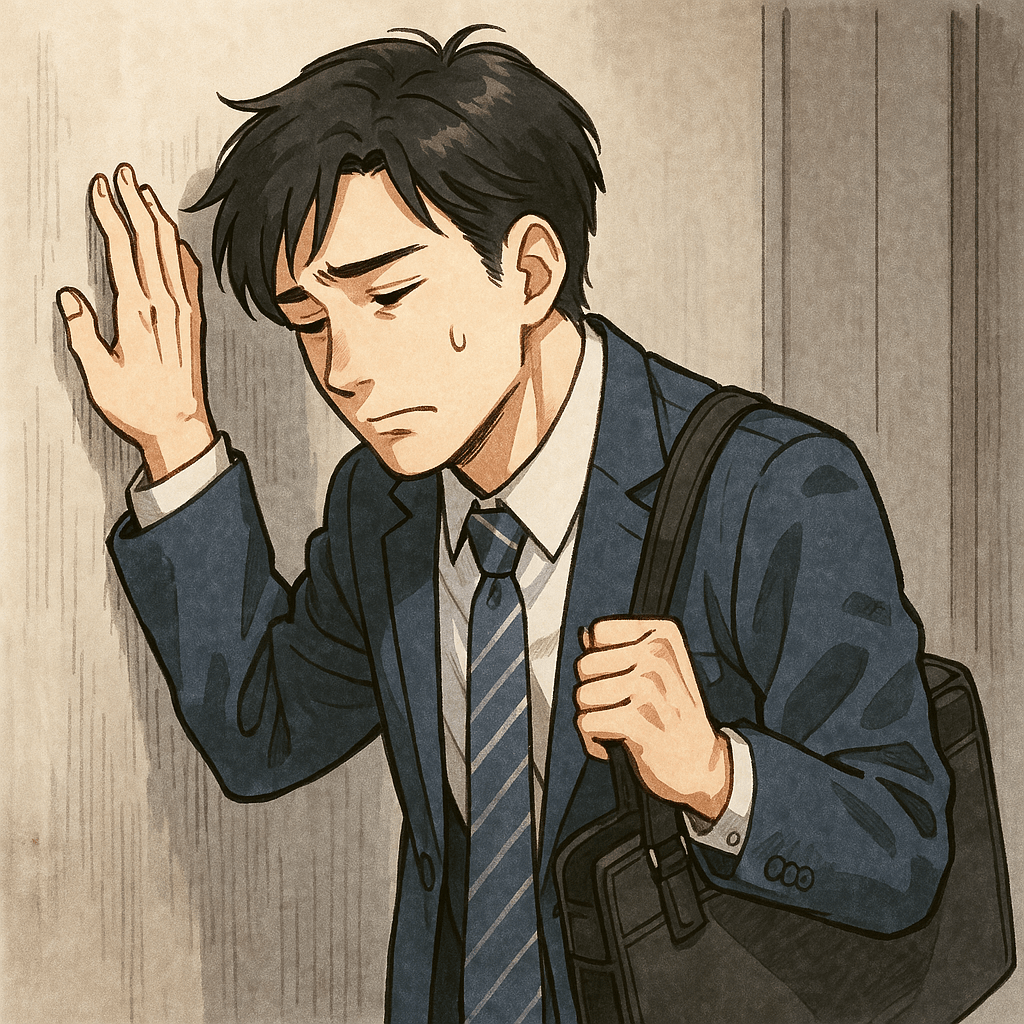
離職率が高い会社は、「働き続けたい」と思える理由が見つからない職場環境であることが多く、「辞めたくなるのは当然」と思われがちです。
実際に、辞めたいと言われる会社にはいくつかの共通点があります。
理由①:人間関係に問題がある
もっとも多い原因のひとつが「人間関係」です。
上司のパワハラ・モラハラ、派閥争い、陰口文化など、職場の雰囲気が悪ければ、いくら待遇が良くても長く働くのは難しくなります。
特に中小企業やベンチャーでは、人数が少ない分、人間関係のトラブルが直接ストレスに直結します。
「あの人と毎日顔を合わせるのがしんどい」と思ってしまえば、離職はすぐに現実になります。
理由②:労働環境が過酷すぎる
長時間労働、休日出勤、有休が取れない、サービス残業が当たり前──こういった労働環境の悪さも、離職率が高くなる原因です。
特にブラック企業にありがちなのが「離職してもすぐ補充できる」という考え方。
人材を“消耗品”のように扱うため、社員の不満は溜まる一方になります。
また、ワークライフバランスが崩れると、仕事以外の生活に支障が出てしまい、心身ともに限界を迎えて退職する人も多くなります。
理由③:キャリアの見通しが立たない
社員のモチベーションを支えるのは、「この会社で成長できる」という希望です。
しかし、
- 教育制度が整っていない
- 昇進の基準が不透明
- 自分の将来像が描けない
といった環境では、どれだけ頑張っても先が見えず、やがて「ここにいても意味がない」と感じてしまいます。
特に若手社員は、自分のキャリアにシビアです。
と思えば、迷わず転職を選ぶ傾向があります。
理由④:理念と現場のギャップが大きい
「社員を大切にします」「風通しの良い職場です」
といった理念やスローガンが、現場でまったく実現されていない会社も要注意です。
たとえば、
- 上司に意見を言ったら評価が下がった
- 成果よりも忖度が評価される
- トップだけがいい思いをしている
といった実態がある場合、社員は理念とのギャップに強い不信感を抱きます。
と気づいた瞬間、人は離れていきます。
理由⑤:優秀な人ほど先に辞めていく
離職率の高い会社では、なぜか「優秀な人からいなくなる」という現象がよく起きます。
- 評価制度が適切でない
- 発言力がない
- スキルを発揮する場がない
といった理由で、成長意欲の高い人が見切りをつけてしまうのです。
結果として、残るのは「何も言わず流される人」や「転職が難しい人」ばかりになり、組織全体のレベルが下がり、ますます人が辞めていくという悪循環に陥ります。
【総括】辞めたい理由が“構造的”になっていないかを見極める
離職率が高い会社では、社員が辞める理由が個人の問題ではなく、組織の構造そのものに起因しているケースが多いです。
- 人間関係
- 労働時間
- キャリアの見通し
- 評価制度
- 経営と現場の乖離
これらが複合的に絡んでいる職場では、表面上は大丈夫そうに見えても、中に入ってみると数ヶ月で心が擦り減ることも少なくありません。
もしあなたが転職先として検討している会社に「離職率が高い」という情報があるなら、こうした背景をしっかり調べて、冷静に判断するようにしましょう。
1年で5人以上辞める会社は辞めるべき?
社員数によっては、辞めたほうがいい可能性が高いです。
特に中小規模の会社で1年に5人以上辞める場合、それは単なる偶然ではなく、何らかの“構造的な問題”を抱えていることが多いです。
社員数に対する「5人」の重みを考える
たとえば、社員数が20名規模の会社で5人が辞めたとしたら、実に25%が1年で離職していることになります。
これは業界全体から見てもかなり高い水準であり、放置できないレベルの離職率です。
逆に社員数が1,000名を超えるような大企業で5人辞めたとしても、それは0.5%にすぎず、特別に高い離職率とは言えません。
つまり「5人」という数字だけを見るのではなく、全体の規模感に対して何%が辞めているのかを考えることが大切です。
高い離職率の背景には“見えない問題”が潜んでいる
なぜそんなに辞めているのか?
そこには、外からでは見えないような問題が隠れているケースがあります。
- 上司のマネジメントが破綻している
- ノルマやプレッシャーが極端に強い
- 教育がないまま放置されている
- 評価が不公平でやる気が奪われる
- 社内ルールがあいまい、場当たり的に変わる
こうした“働きにくさ”が積もり積もって退職者を生み出します。
特に中小企業やベンチャーでは、経営者のスタンスが原因になっていることも多く、改善されにくいのが現実です。
辞めていくのは「問題社員」だけとは限らない
よくある会社の言い訳に
というものがあります。
確かに、仕事に対する姿勢や価値観が合わずに去っていく人もいるでしょう。
しかし、実際には「優秀な人ほど先に辞める」という逆転現象が起きていることも多いのです。
成長機会がない、自分の力が活かせない、職場に希望が持てないと感じたとき、感度の高い社員ほど見切りをつけて去っていく傾向があります。
つまり、1年で5人以上辞めている会社が「問題のある人ばかりが辞めている」と考えるのは、非常に危うい見方です。
残っている社員の声にも注意が必要
離職率の高さを「自分には関係ない」と考えている人もいますが、すでに残っている社員の言動や雰囲気にも注目すべきです。
- ネガティブな話が多い
- 愚痴や陰口が飛び交っている
- 明らかにやる気がない
- 「どうせ辞めるし」と開き直っている
こうした空気が職場に蔓延していたら、次に辞めるのはあなたかもしれません。
“辞めない人が健全”とは限らず、むしろ「惰性で居続けている」場合も少なくないのです。
【総括】「5人」はサイン。会社の本質を見極めて行動を
1年で5人以上が辞めている会社は、組織として何らかの問題を抱えているサインです。
- 会社の規模に対してどれくらいの割合か?
- なぜ人が辞めているのか?
- 残っている人たちはどう感じているのか?
これらを冷静に分析し、自分のキャリアや働き方に照らし合わせたうえで、
「今すぐ辞めるべきか」
「もう少し様子を見るか」
を判断しましょう。
もし、あなたが「このままでは自分まで疲弊する」と感じているなら、環境を変える勇気を持つことも、立派な選択肢の一つです。